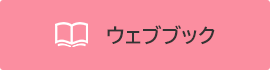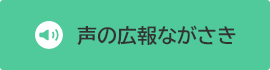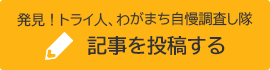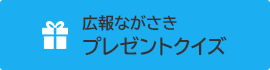ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
長崎の郷土芸能 「間の瀬狂言」
長崎には、各地で受け継がれてきた、さまざまな芸能があります。祭りや神事で披露される芸能は、その土地に根差した地域の特色や風習が取り入れられ、独自に発展してきました。今回は、郷土芸能のひとつ、「間の瀬狂言」について紹介します。
間の瀬狂言は、滝の観音の門前と呼ばれる小集落に伝わる狂言まじりの猿浮立で、県の無形民俗文化財に指定されています。伝承によると、動作・道具などは室町期から受け継がれてきたものであると言われています。観音寺を創始するときにも、この狂言を奉納したと言われていて、代々伝えられてきた大太鼓には、「元禄8年(1695年)観音寺」の銘が刻まれています。
笛・太鼓・鉦の調子に合わせて、茶道で使われる立道具やササラを使った踊りが始まります。その後、根治平と与五郎の掛け合いが行われ、「見猿」「聞か猿」「言猿」という3匹の猿の踊りが始まります。リズミカルな笛囃子とテンポの良い大太鼓、鉦の流れに乗って狂言が行われます。
9月28日(日曜日)に市民会館で行われる長崎郷土芸能大会で、間の瀬狂言が披露されます。他にも、地域の枠を超え、6団体が出演するこの大会は無料で観覧できます。ぜひこの機会に長崎の郷土芸能に触れてみませんか?
文化財課 学芸員 田中

▲猿浮立の様子

▲奉納踊りの様子