ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
建築基準法における一般的な手続きの流れを説明します。
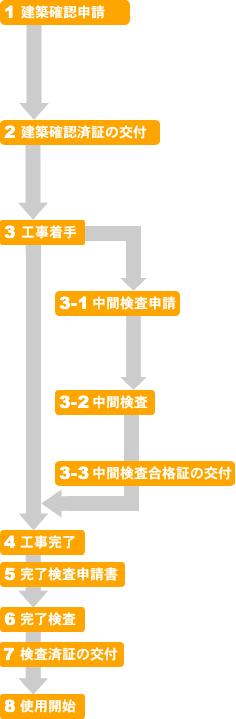
1 建物等の建築などを行うときには、事前にその計画が法令等に適合しているかどうかを確認するため、建築確認申請書を長崎市・建築指導課若しくは指定確認検査機関に提出し、その確認を受ける必要があります。市の場合の審査期限は7日間、規模・用途・構造によっては35日間となっています。
2 上記の確認申請書により審査・確認され、その計画内容が法令等に適合していることを証する建築確認済証の交付を受けなければ、工事に着手する事ができません。
3 建物等の建築などを行うときは、工事現場の見やすい場所に、建築確認済の表示板を表示しなければなりません。
3-1 建築基準法で規定する建物は、中間検査を受けなければなりません。そのため、長崎市・建築指導課若しくは指定確認検査機関に中間検査申請をする必要があります。
3-3 中間検査合格証の交付を受けなければ、工事を進めることができません。
4・5 建物等の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築指導課若しくは指定確認検査機関に、完了検査申請書を申請しなければなりません。
7 完了検査を受け、検査に合格した場合、その旨を証する検査済証を交付します。
8 工事が完了した建物は、検査済証の交付を受けなければ、使用する事ができない場合もあります。
ポイント
- 建築基準法は、建築物や建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
- 建物などを建てるときには、専門の建築士へご相談するか建築指導課までお問い合わせください。
- ほんの少し増築したい、車庫をつけたい、吹き抜け部分に床をはりたい、屋根裏部屋を設けたいなど、敷地や建物の利用には、建築確認申請が必要な場合があります。建築基準法や建築基準関係規定については、専門の建築士や、建築指導課に相談されてください。仮に、申請が不要であったとしても、建築基準法および建築基準関係規定に適合していなくてはいけません。
- 建築士が行う役割として、設計や工事監理などがあります。
設計は、建築基準法などを遵守し、建築物等の安全性や機能性などを考慮し、設計図書などを作成します。
工事監理は、建築主の立場に立って、工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかの確認を行います。工事監理は、設計者に依頼されるケースもありますが、別の建築士を選定されても構いません。 - 建築主は、建築確認申請書・建築確認済証・検査済証(建物によっては中間検査合格証も含む) の手続きおよび交付を必ず受け、大切に保管してください。
将来における建物の増築等の計画に、これらの書類が必要となります。
また、建物を売買される等の際には、これらの書類を確認し、必ず引き継いでください。 - 住宅などの建築物を購入したり、賃借される際に、その建築物が建築基準法上、どのような建築物かを確認する方法として、建築計画概要書等の閲覧という制度がありますので、ご活用ください。



