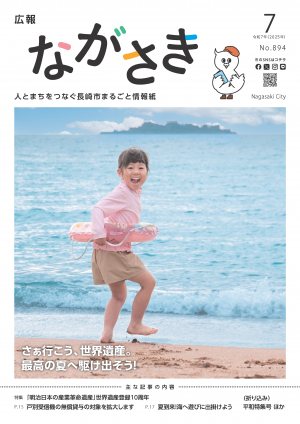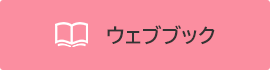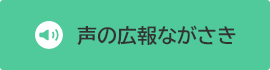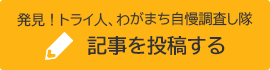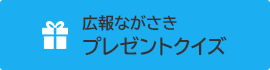ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
弥生時代に栄えた「貝の道」
沖縄や奄美などの温暖な南西諸島では、 ゴホウラやイモガイという大型の貝が生息しています。これらの貝は、表面が白っぽい色合いで、磨くとつやつやとした光沢を帯びます。中国などで重宝されていた玉と近しい質感だったので、 装飾品の材料としして好まれていました。 弥生時代の前半頃には、これらの貝を材料とした貝輪(ブレスレット)が、北部九州を中心とした地域で流行しました。市内にも出土例があり、深堀遺跡では、右手首にイモガイ製の貝輪をつけて埋葬された女性が見つかっています。この女性は、碧玉製管玉(へききょくせいくだたま)(緑色の宝石でできたビーズ玉)を身に着けていて、特別な人物だったと推測されます。


弥生人たちは、 海を介した交易によって、地元では採れない貝を入手して九州で装飾品に加工していました。この交易ルートは「貝の道」と呼ばれ、当初その中心的役割を担っていたのは、現在の長崎県周辺の海岸部に住んでいた人々だったと考えられています。平野部では稲作中心の生活が営まれていた時代でしたが海外に暮らす人々は東シナ海を中心とした海域を往来し、活発な交易を行っていました。深堀地域センターの近くにある深堀貝塚遺跡資料館は、今年4月に全面的な展示替えを行い、新たにイモガイ製の貝輪を展示に加えました。入館無料で、実物を見ることができます。この機会にぜひお越しください!
文化財課 学芸員 竹村