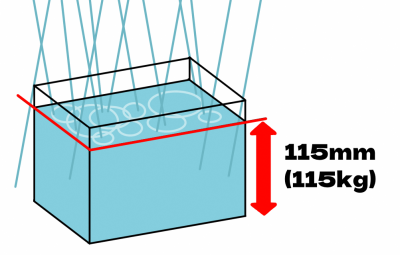本文
長崎大水害について知ろう!
長崎大水害(ながさきだいすいがい)とは?
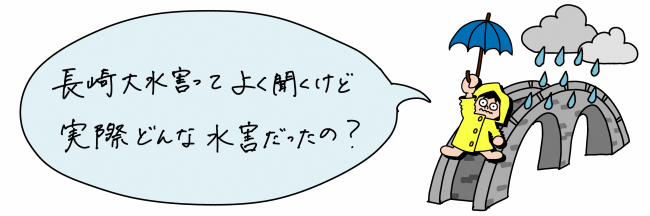
長崎大水害とは、1982年7月23日に長崎県をおそった集中豪雨(しゅうちゅうごうう)により発生した、今まで見たことがないような大きな水害だよ。長崎市では1時間に115mmというものすごい雨がふって、いろいろなところで土砂がくずれたり、川があふれたりして、大きな被害をうけたんだ(ちなみに長崎市のとなりにある長与町では1時間に187mmという、これまで日本で記録された中で一番多い雨がふったんだよ)。
日本で一番古い石造りアーチ橋の「眼鏡橋(めがねばし)」も、写真で見て分かるように、歩いて渡ることもできないくらいにこわれてしまったんだよ。

「1時間に115mmの雨」ってどれくらいの雨?
1時間にふった雨がそのままたまった場合、115mmの高さになるほどの雨の量ということ。たとえば1平方メートルの範囲に115mmの雨がふった場合、115mmの高さまで水がたまり、その水の量は115リットル(約115kg)にもなるんだ。
長崎大水害で、雨がふりはじめてから次の日までにふった雨の量は約600mm。7月の平均的な雨の量はひと月で300mmくらいなので、たったの2日で7月にふる雨の2倍の雨がふったことになるんだよ。
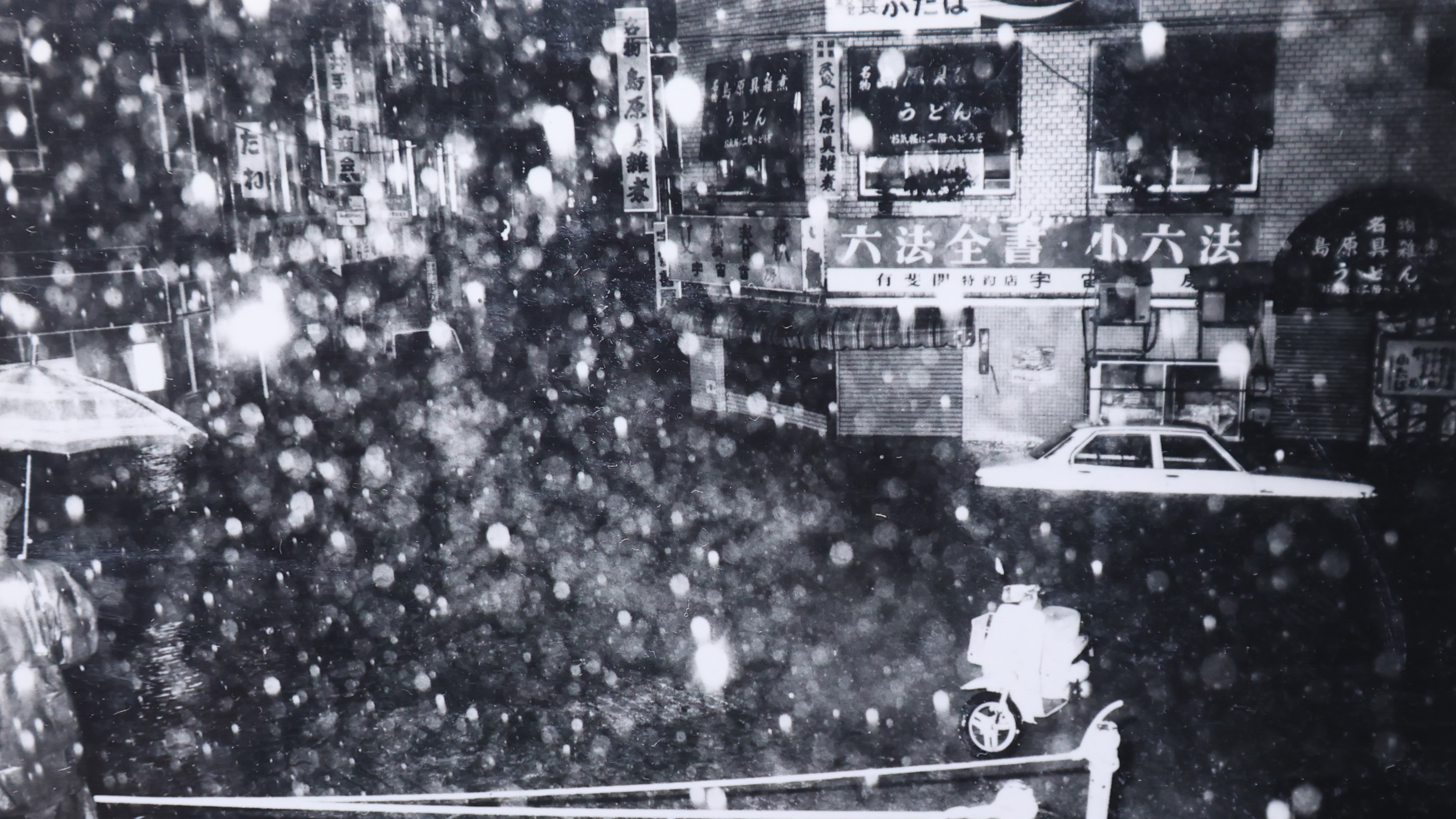
大水害当日の雨のようす(築町)
| 雨の量 | ふり方のイメージ |
|---|---|
| 10~20mm | やや強い雨(ザーザーとふる) |
| 20~30mm | 強い雨(どしゃぶり) |
| 30~50mm | 激しい雨(バケツをひっくり返したようにふる) |
| 50~80mm | 非常に激しい雨(滝のようにふる) |
| 80mm~ | 猛烈な雨(息苦しくなるような圧迫感や恐怖を感じるようにふる) |
長崎大水害の被害について
翌7月24日の長崎は、災害前からは想像もつかない姿になっていたんだ…
長崎大水害で亡くなった人と見つかっていない人は合わせて299人。さらに斜面地が崩れて道路にたくさんの石や土が流れ込み、流された家のがれきや車が積み重なっているような状態だったんだ。
長崎大水害は多くの尊い人命と財産を奪い、長崎のお店や会社、電気や水道など、市民の生活にとても大きな被害をあたえたんだよ。

写真左:浜町アーケード、写真右:矢上地区

写真左:川平地区、写真右:芒塚(すすきづか)地区

写真左:本河内(ほんごうち)地区、写真右:鳴滝(なるたき)地区
| 内容 | どのくらい被害があったか |
|---|---|
| 亡くなった人など | 県内299人(約9割の人が土砂災害により亡くなりました) |
| 家や建物の被害 | 2万7,331世帯 |
| がけ崩れ | 535カ所 |
| 道路の被害 | 1,113カ所 |
| 水道・ガス・電気の被害 | 水道:9万3000戸、ガス:4万2000戸、電気:6万2000戸 |
| 被害の合計金額 | 2,119億円 |
1日でも早く元の長崎市に戻すために

洪水になったときと水が引いた後のようす(東長崎地区)
7月24日、雨が上がった後に残されていたのは流されてきた大量のゴミや土砂。1日でも早く元の暮らしを取り戻すために、まずは大量のゴミや土砂を片付けることが必要だったんだ。長崎のまちを元通りにするために、市民みんなで地道な作業に取り組んだんだよ。

長崎水害ででたゴミの量は、長崎市民が1年間に出すゴミの量と同じくらいと言われ、その片付け作業はたいへんだったんだ。特に、中島川や浦上川のまわりでは、ゴミや土砂が積み重なって、交通のじゃまになっていたため、学校のグラウンドを一時的にゴミを集める場所として使っていたんだよ。

さらに、生活への影響が大きかったから、こわれてしまった道路や橋もすぐに修理しなければならなかったんだ。
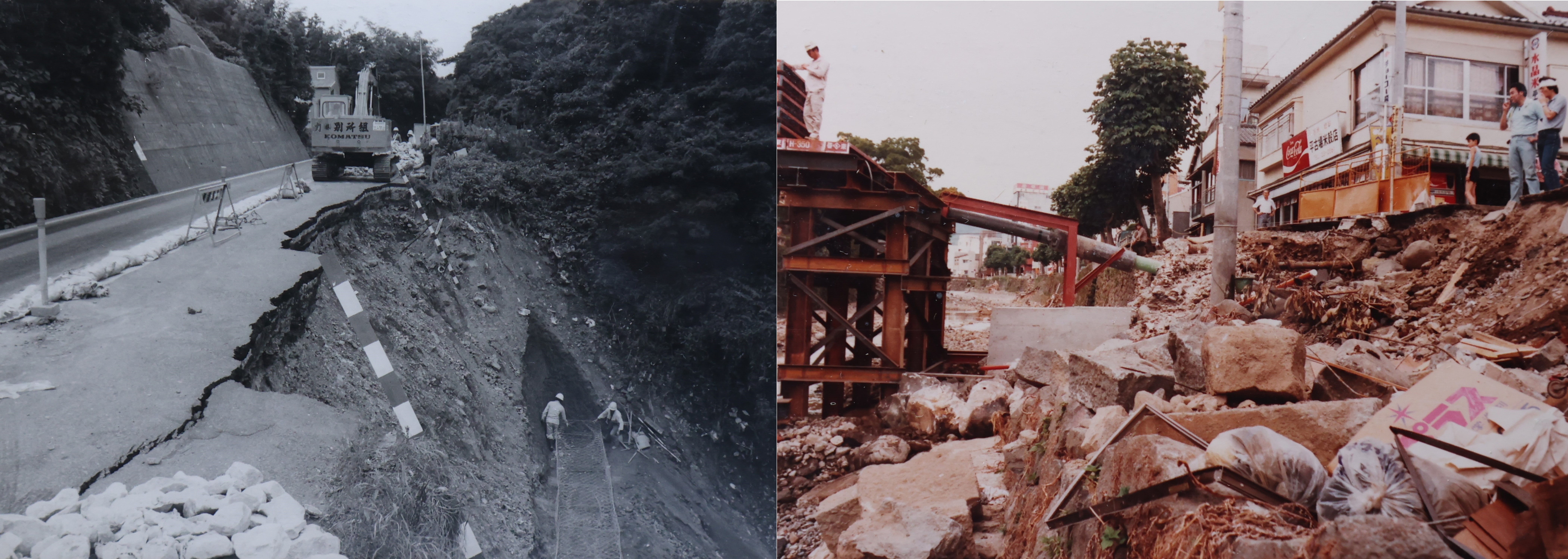
写真左:道路の修理のようす(茂木地区)、写真右:橋の修理のようす(中島川)

道路の修理前と修理後(日見トンネル前)
長崎大水害はなぜおこったのか
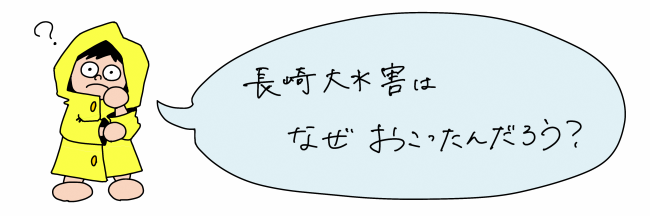
いろいろな要因が重なりました
長崎市では、7月23日の数日前から雨がふり続いていた。その雨が地面にたっぷりしみ込んでいたところに、短時間に一気にふった雨が重なって、市内のいろいろなところでがけ崩れや山崩れが発生したんだ。さらに満潮の時間とも重なったことから、川があふれて大水害となってしまったんだよ。
避難や災害対応が難しい状況でした
家に帰る時間や夕ご飯の時間に、短い時間でとても強い雨がふったこと、道路が水につかって交通がマヒしたこと、7月10日から何度も大雨に関する警報(けいほう)が出されていて、市民が慣れてしまっていたことから、避難するのが遅くなってしまったんだ。その後、夜にかけて雨は強まり、停電が発生し、さらに避難が難しくなってしまったんだよ。

市役所ロビーも一時的な避難所に
いざという時に備えよう!
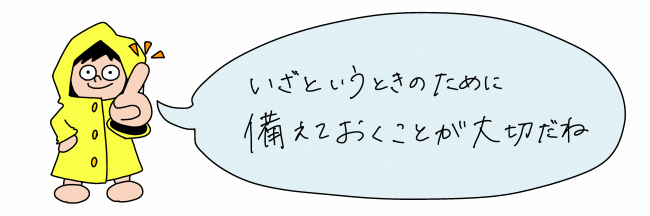
「どのタイミングで避難するのか」「どこに避難するのか」「何を持って避難するのか」を前もって決めておくことは、避難するときにとても大切なことだよ。日頃から、いざという時にどこに避難するかなど「マイ避難所」について考えておこうね!
マイ避難所について詳しくはこちら