新大工町曳壇尻
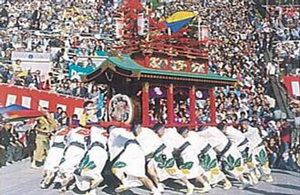
- 所在地 長崎市新大工町
- 保持団体 新大工町くんち奉賛会
- 組織 新大工町くんち奉賛会が運営に当たっている。
- 上演期間 10月7日・8日・9日(踊町年番の年)
- 上演場所 諏訪神社境内、お旅所(大波止)、中央公園、八坂神社
- 備考 詩舞(若い女性による)が付く。
由来
春日大社の前庭を模した「だし」で、川船の船首部分を取ったような構造の曳き物である。明治34(1901)年に諏訪神社に奉納したという記録が残る。
芸能の構成
曳壇尻は、白采一人、添采四人、根曳二十人で曳き廻す。囃子方は子ども六人で曳壇尻に乗り、大太鼓、〆太鼓、大鉦、小鉦からなる。