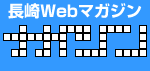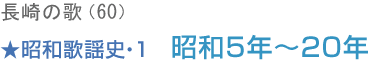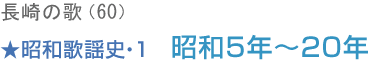
文・宮川密義 |
|
今回からは「昭和歌謡史」と題して、昭和期にレコードやテープ、CDなどで発表された長崎の歌を、その時代背景をたどりながら紹介していきます。(本文および表中の青文字はバックナンバーにリンクしています) |
*レコード時代開幕
日本に登場したレコード会社は明治42年(1909)の日米蓄音器商会が第一号で、翌43年に日本蓄音器商会に改称して、鷲印・ニッポノホン大仏印レコード(現在の日本コロムビアの前身)を発売。昭和に入り、ビクターが2年(1927)、コロムビアが4年に日蓄から新発足。ポリドールは4年、キング5年、テイチクが9年に創立しました。
長崎の歌のレコードは昭和5年(1930)から出ています。その第一号は長崎出身の作詞家・西岡水朗(にしおか・すいろう)の出世作「雲仙音頭」で、その片面に同じ西岡水朗作詞の「長崎小唄」が入っています。長崎市内の歌としては「長崎小唄」が第1号というわけです。
以下の表は、長崎の歌のうち長崎市内をテーマにした全国盤から、主な歌を取り上げました。
【昭和5年(1930)】 全8曲 |
|
|
 |
 |
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
3 |
雲仙音頭 |
葭町二三吉 |
西岡水朗 |
杉山長谷夫 |
| 2 |
3 |
長崎小唄 |
葭町二三吉 |
西岡水朗 |
杉山長谷夫 |
| 3 |
3 |
長崎節 |
植森たかを |
西岡水朗 |
杉山長谷夫 |
| 4 |
3 |
片しぶき |
植森たかを |
西岡水朗 |
杉山長谷夫 |
| 5 |
9 |
長崎ぶらぶら節 |
凸助 |
民謡 |
民謡 |
| 6 |
9 |
長崎ノンノコ節 |
凸助 |
民謡 |
民謡 |
| 7 |
9 |
長崎港節 |
凸助 |
民謡 |
民謡 |
| 8 |
9 |
長崎甚句 |
一二 |
民謡 |
民謡 |
※「長崎ぶらぶら節」や「長崎甚句」などは民謡ですが、レコード黎明期に限り例外として取り上げました。
●主な出来事 |
前年(昭和4年)10月にニューヨーク株式の大暴落をきっかけに世界恐慌が始まり、日本にも波及して失業者が町にあふれました。町には刹那的な生き方を反映してカフェー、バー、ダンスホールなどが急増、“エログロ・ナンセンス時代”ともいわれました。社交ダンスが流行しジャズが歌われ、流行歌は「愛して頂戴」のような“ネエ小唄”が登場します。
長崎では造船不況が押し寄せる一方、ダンスが流行、翌年2月には長崎署が禁止しています。歌の方は、大正から昭和にかけて見られた「新民謡運動」の流れで、民謡もの(音頭、小唄)でレコード時代が始まり、その流れで長崎町検番の芸妓・凸助(でこすけ)が「長崎ぶらぶら節」など4曲をレコードに吹き込んでいます。
|
【昭和6年(1931)】 全17曲から6曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
2 |
ぶらぶら節 |
愛八 |
民謡 |
民謡 |
| 2 |
2 |
長崎浜節 |
愛八 |
古賀十二郎 |
愛八 |
| 3 |
6 |
ながさき |
根本美津子 |
林 柳波 |
藤井清水 |
| 4 |
6 |
和蘭陀船 |
羽衣歌子 |
西岡水朗 |
藤井清水 |
| 5 |
8 |
大九州行進曲 |
黒田 進 |
畑 喜代司 |
藤枝正文 |
| 6 |
8 |
片しぶき(再版) |
ベルトラメリー能子 |
西岡水朗 |
杉山長谷夫 |
※ほかに「天然の美」「麗しき天然」「佐世保小唄」「佐世保行進曲」「軍港行進曲」「加津佐小唄」「雲仙新曲」「佐世保メロディ」など11曲。
●主な出来事 |
|
 |
 |
9月に柳条溝事件に端を発して満州事変が始まりました。
歌謡界では“古賀メロディ”が人気を集めました。
長崎では不況のため三菱造船、兵器製作所、電機で人員削減が行われ、松が枝町の香港上海銀行長崎支店が閉鎖、長崎港の貿易も閑散となります。レコードは時局を反映して「佐世保行進曲」など軍港佐世保の歌が7曲出ており、長崎ものは愛八の「ぶらぶら節」と「浜節」など5曲。
|
【昭和7年(1932)】 全32曲から9曲 |
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
1 |
長崎夜曲 |
貝塚 正 |
西岡水朗 |
山内冷晃 |
| 2 |
1 |
胡弓ひく乙女 |
水島京子 |
西川 林之助 |
高峰龍夫 |
| 3 |
7 |
九州小唄 |
三島一声 |
九州日報社当選歌 |
藤井清水 |
| 4 |
7 |
九州小唄 |
赤坂小梅 |
九州日報社当選歌 |
藤井清水 |
| 5 |
8 |
居留地の娘 |
天野喜代子 |
? |
? |
| 6 |
8 |
長崎新小唄 |
大和田きく |
江 博二 |
藤井清水 |
| 7 |
8 |
長崎行進曲 |
小川 洋 |
坂田 三郎 |
阪東政一 |
| 8 |
10 |
不知火小唄 |
南 一郎 |
伊藤 隆造 |
清瀬保二 |
| 9 |
10 |
不知火小唄 |
赤坂小梅 |
伊藤 隆造 |
清瀬保二 |
※ほかに「爆弾三勇士の歌」など三勇士讃歌が22曲と「橘中佐」があります。
●主な出来事 |
1月に上海事変がぼっ発、3月に満州国が建国を宣言。国内では「五.一五事件」で犬養首相が暗殺されています。
流行歌は前年のヒット曲「酒は泪か溜息か」の古賀メロディに続き、小唄勝太郎の「島の娘」などの“ハァ小唄”がヒットしました。
長崎では日華連絡船で上海からの避難者が相次ぎました。
歌は時局を反映して「爆弾三勇士」を称える歌が各社からレコードが出ています。三勇士のうち2人は長崎県出身者であり、長崎の歌に取り入れましたが、ここでは表から除外しました。
|
【昭和8年(1933)】 全11曲から9曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
? |
お蝶夫人「歎きの蝶」 |
渡辺光子 |
大沼 萍 |
江口夜詩 |
| 2 |
? |
お蝶夫人「いとしの蝶よ」 |
館野信平 |
西川 林之助 |
江口夜詩 |
| 3 |
? |
長崎ぴんとこ節 |
作 栄 |
西岡水朗 |
藤井清水 |
| 4 |
1 |
和蘭陀船 |
ベルトラメリー能子 |
北原白秋 |
山田耕筰 |
| 5 |
5 |
お蝶夫人の唄 |
ミス・コロムビア |
西条八十 |
古賀政男 |
| 6 |
5 |
マダム・バタフライの唄 |
淡谷のり子 |
西条八十 |
佐々紅華 |
| 7 |
12 |
長崎市歌 |
伊藤武雄 |
長崎市教育会編 |
橋本国彦 |
| 8 |
12 |
崎陽小唄 |
赤坂小梅 |
乳井三郎 |
大村能章 |
| 9 |
12 |
長崎博覧会の歌 |
横山良三 |
渡部龍夫 |
大村能章 |
※ほかに「幽峡雲仙(A)」「幽峡雲仙(B)」があります。
●主な出来事 |
1月ドイツにヒットラー内閣成立。3月に日本が国際連盟を脱退、政府は国民に“非常時の覚悟”を説きますが、巷では享楽的な歌が流行。内務省は8月にレコード検閲を開始、特に官能的な歌は発売禁止にします。“ネェ小唄”は姿を消し、「東京音頭」など音頭ものが流行しました。
長崎では景気回復で年初から活況を取り戻しました。9月にNHK長崎放送局が開局、歌や芸能などのほか、10月の長崎くんちもラジオで全国に中継放送しました。
歌では、アメリカ映画「お蝶夫人」が日本で封切られ、それに合わせてレコードも発売されました。「長崎市歌」も12月に誕生。翌9年の長崎観光博覧会にちなむ歌のレコード発表が始まりました。この年は「東京音頭」ブームが波及して九州各地で盆踊りあり、九州の歌が相次ぎました。
|
|
 |
 |
【昭和9年(1934)】 全34曲から9曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
? |
長崎県名所行進曲 |
小野喜代子 |
原 善磨 |
瀬戸口辰弥 |
| 2 |
1 |
長崎恋しや |
市丸 |
西条八十 |
中山晋平 |
| 3 |
1 |
長崎スッチョイ |
三島一声 |
吉田藤十郎 |
中山晋平 |
| 4 |
4 |
長崎小唄 |
藤山一郎 |
平山蘆江 |
中山晋平 |
| 5 |
4 |
長崎音頭 |
美ち奴 |
平山蘆江 |
斎藤佳三郎 |
| 6 |
4 |
長崎しぐれ |
結城 浩 |
塚本篤夫 |
松永和夫 |
| 7 |
4 |
南蛮小唄 |
山路不二男 |
平山蘆江 |
斎藤佳三郎 |
| 8 |
4 |
長崎音頭 |
小唄勝太郎 |
西条八十 |
中山晋平 |
| 9 |
6 |
NAGASAKI |
ミルス・ブラザーズ |
モート・ディクソン |
ハリー・ウォーレン |
※ほかに「佐世保小夜曲」など佐世保と軍港の歌9曲、同名異曲の「九州音頭」6曲など九州もの15曲、「雲仙音頭」と「招く雲仙」「恋の不知火」があります。
表の9「NAGASAKI」はアメリカの映画作曲家がオペラの「マダム・バタフライ」にアイデアを借りて作曲したジャズ・ソングです。
●主な出来事 |
国内では函館市で大火(3月、死者2,015人)、室戸台風(9月、死者2,866人)、東北地方冷害(11月)と災害が続きました。
県内では3月12日、水雷艇「友鶴」が佐世保港外で転覆、死者100人。3月16日、雲仙国立公園が正式に決定。3月25日、長崎と雲仙の2会場で長崎観光博覧会が開幕、90日間にわたって賑わいました。その盛り上げのために「長崎音頭」などが作られ、長崎くんちの奉納踊りにもなっている「阿蘭陀万歳」も博覧会の演芸館で初めて披露されました。
|
【昭和10年(1935)】 全23曲から11曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
? |
長崎バッテン節 |
虎龍 |
西岡水朗 |
近藤十九二 |
| 2 |
? |
長崎よいとこ |
米一 |
西岡水朗 |
近藤十九二 |
| 3 |
5 |
春の長崎 |
喜代三 |
渡部龍夫 |
山田栄一 |
| 4 |
5 |
長崎行進曲 |
東海林太郎 |
渡部龍夫 |
大村能章 |
| 5 |
5 |
よかばい唄 |
有島通男 |
土方 喬 |
深井史郎 |
| 6 |
6 |
長崎みなと祭小唄 |
喜代三 |
八雲幽鳥 |
山田栄一 |
| 7 |
6 |
長崎開港記念歌 |
東海林太郎 |
川上和泉 |
斎藤佳三郎 |
| 8 |
8 |
博多小女郎浪枕 |
東海林太郎 |
藤田まさと |
大村能章 |
| 9 |
9 |
長崎唐人ばやし |
ミス・コロムビア |
西岡水朗 |
古関裕而 |
| 10 |
11 |
蝶々さんの唄 |
小唄勝太郎 |
佐伯孝夫 |
杉山長谷夫 |
| 11 |
11 |
蝶々さんの子守唄 |
四家文子 |
佐伯孝夫 |
杉山長谷夫 |
※ほかに「軍港祭」「佐世保軍港ぶし」、「九州想えば」など九州もの5曲、「島原音頭」と「島原小唄」も出ています。表の8「博多小女郎浪枕」は近松門左衛門作の浄瑠璃「博多小女郎波枕」を基に作られたもので、長崎の海賊・毛剃九右衛門も登場しています。
●主な出来事 |
国内外とも比較的平穏な年でしたが、県内では端島炭坑でガス爆発があり死者25人、北松福島村で70戸を全焼する大火がありました。この年の臨時国勢調査で長崎の人口は21万2,077人と判明しました。
流行歌は全国で「野崎小唄」「赤城の子守唄」がヒット。長崎では「東京行進曲」の人気が波及、「長崎行進曲」がレコードになりました。
一方、昭和8年に始まる“蝶々夫人”の人気はレコード界で続いており、昭和30年代まで多くの歌手が吹き込みました。
|
【昭和11年(1936)】 全10曲から4曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
? |
阿蘭陀船の唄 |
東光子 |
山田としを |
南 良介 |
| 2 |
2 |
お蝶夫人の唄 |
東海林太郎 |
サトウハチロー |
大村能章 |
| 3 |
2 |
恋の蝶々 |
日本橋きみ栄 |
西岡水朗 |
阿部武雄 |
| 4 |
7 |
長崎造船所歌 |
中野忠晴 |
北原白秋 |
山田耕筰 |
※ほかに「祈る島原」など島原もの3曲、「美わしき天然」「玄海ぶし」「ナガサキ」。
●主な出来事 |
1月早々に日本がロンドン軍縮会議を脱退。国内では2月に陸軍の青年将校らによるクーデター「二・二六事件」があり、東京に戒厳令が敷かれ、29日に鎮定したものの、軍部の政治支配が強まりました。ほかに阿部定猟奇事件(5月)、ベルリンオリンピック(8月)。
この年、ラジオで「椰子の実」「朝」など国民歌謡の放送が始まりましたが、一方で「忘れちゃいやよ」などが好まれ、“官能的歌唱”として発売禁止になる歌も相次ぎました。
長崎の歌は“蝶々夫人”の歌が続きましたが、全体に低調でした。
|
|
 |
 |
|
|
| *日中戦争時代 |
【昭和12年(1937)】 全31曲から13曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
3 |
踏絵 |
東海林太郎 |
佐藤惣之助 |
長津義司 |
| 2 |
3 |
和蘭陀船 |
大川澄子 |
北原白秋 |
山田耕筰 |
| 3 |
3 |
長崎情歌 |
音丸 |
久保田宵二 |
竹岡信幸 |
| 4 |
3 |
長崎の春 |
井崎加代子 |
小石一栄 |
宇賀神美津男 |
| 5 |
3 |
じゃがたら文 |
関 種子 |
大木惇夫 |
阿部武雄 |
| 6 |
3 |
恋の唐人船 |
霧島 昇 |
久保田宵二 |
竹岡信幸 |
| 7 |
4 |
からゆきさんの唄 |
林伊佐緒 |
時雨音羽 |
細川潤一 |
| 8 |
7 |
胸の十字架 |
青葉笙子 |
宮城勝夫 |
森 儀八郎 |
| 9 |
8 |
お蝶夫人 |
内本 実 |
小野七郎 |
池 譲 |
| 10 |
11 |
涙の十字架 |
青葉笙子 |
佐藤惣之助 |
長津義司 |
| 11 |
11 |
この母この子 |
楠木繁夫、
朗読・夏川静江 |
佐藤惣之助 |
古賀政男 |
| 12 |
11 |
山内中尉の母 |
藤山一郎 |
佐藤惣之助 |
古賀政男 |
| 13 |
12 |
忠烈山内中尉の母 |
関 種子 |
松坂直美 |
長津義司 |
※このほか、「美しき天然」や「橘中佐」「防人の歌」「肉弾ぶし」など戦意昂揚をねらう歌、江戸時代に中国や朝鮮沿岸を侵略した海賊を歌う「八幡船(ばはんせん)」もの、「躍進九州」など九州ものなどが出ています。
●主な出来事 |
7月に蘆溝橋事件を契機に日中戦争が始まり、8月に第二次上海事変に波及。9月、政府は国民精神総動員運動を開始。長崎・浦上両駅は出征兵士を見送る市民で埋まり、三菱長崎造船所は戦時体制に切り替えられ、翌13年2月からは戦艦「武蔵」の建造が始まります。
歌謡界は事変勃発後「軍国の母」など軍歌や軍国歌謡が続出します。
|
【昭和13年(1938)】 全4曲から4曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
1 |
八幡船 |
東海林太郎 |
伊藤靜馬 |
阿部武雄 |
| 2 |
2 |
玄海の月 |
東海林太郎 |
渋谷白涙 |
堀とおる |
| 3 |
9 |
玄海しぶき |
塩まさる |
島田芳文 |
佐藤長助 |
| 4 |
10 |
八幡船の娘 |
能勢妙子 |
佐伯孝夫 |
塙 六郎 |
●主な出来事 |
4月に国家総動員法を公布、戦時体制がさらに強化されます。金属は兵器製造のため挑発され、竹製スプーン、木製バケツなど代用品時代になり、蓄音器針も鋼鉄使用が禁止されて竹針が登場。
歌は「支那の夜」「満州娘」などの大陸ものや「麦と兵隊」「日の丸行進曲」などがヒット。長崎ものは海を舞台にした4曲だけでした。
|
【昭和14年(1939)】 全14曲から6曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
1 |
任侠ぶし |
美ち奴 |
茂木了次 |
鈴木哲夫 |
| 2 |
1 |
鉄火部隊 |
桜井健二 |
茂木了次 |
鈴木哲夫 |
| 3 |
5 |
長崎むすめ |
金広つぼみ |
若杉雄三郎 |
山田栄一 |
| 4 |
9 |
長崎のお蝶さん |
渡辺はま子 |
藤浦 洸 |
竹岡信幸 |
| 5 |
10 |
港のセレナーデ |
由利あけみ |
梅木三郎 |
塙 六郎 |
| 6 |
10 |
長崎物語 |
由利あけみ |
梅木三郎 |
佐々木俊一 |
※ほかに「九州双六」など九州もの3曲、「玄海舟唄」「島原夜曲」「軍港小唄」など。
●主な出来事 |
5月に満蒙国境で日ソ両軍が交戦、日本軍が大敗したノモンハン事件が発生。9月には英仏の対独宣戦布告で第二次世界大戦勃発。国内では国民徴用令の公布、賃金・価格等統制令、米穀や木炭の配給制が始まり、国民服が流行しました。歌は「父よあなたは強かった」「太平洋行進曲」「空の勇士」など軍国歌謡のほか、「長崎物語」も大ヒット、「長崎のお蝶さん」「上海の花売娘」「九段の母」も歌われました。
|
【昭和15年(1940)】 全10曲から5曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
4 |
あこがれの町 |
伏見信子 |
藤田まさと |
長津義司 |
| 2 |
10 |
オランダ娘 |
星影美沙子 |
福田政夫 |
飯田信夫 |
| 3 |
10 |
居留地の灯 |
上原 敏、浪良通子 |
豊田 徹 |
江口夜詩 |
| 4 |
12 |
長崎ルムバ |
鬼 俊英 |
宇野義樹 |
陸奥 明 |
| 5 |
12 |
オランダ娘 |
服部富子 |
佐伯 龍 |
陸奥 明 |
※「佐世保鎮守府を讃へる歌」「佐世保軍港行進曲」「天然の美」、長崎も出る「上海小唄」「八幡船」があります。
●主な出来事 |
6月に強力な国民再組織を目指す新体制運動が起こり、各政党は解散、10月には大政翼賛会が発会します。9月に日独伊三国同盟に調印、11月には国民の士気を高める紀元二千六百年祈念式典が行われ、「紀元二千六百年」の歌も作られました。また隣組制度が設けられ、歌の「隣組」も出て庶民に受け入れられ、ヒットしました。
長崎では7月から切符制で米や麦の配給が始まり、11月1日には三菱長崎造船所で戦艦「武蔵」が進水しています。
|
|
| *太平洋戦争時代 |
【昭和16年(1941)】 全13曲から9曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
1 |
長崎夜曲 |
東海林太郎 |
矢島寵児 |
島口駒夫 |
| 2 |
1 |
居留地の娘 |
高山美枝子 |
清水みのる |
長津義司 |
| 3 |
2 |
おらんだ草紙 |
霧島 昇 |
野村俊夫 |
古関裕而 |
| 4 |
5 |
しののめ長崎 |
歌上艶子 |
若杉雄三郎 |
東 辰三 |
| 5 |
9 |
夢のオランダ船 |
如月俊夫 |
矢島寵児 |
利根一郎 |
| 6 |
9 |
じゃがたら物語 |
藤原亮子 |
梅木三郎 |
清水保雄 |
| 7 |
9 |
さらば長崎 |
小林千代子 |
矢島寵児 |
利根一郎 |
| 8 |
11 |
唐人船 |
三根耕一 |
松坂直美 |
佐渡暁夫 |
| 9 |
12 |
さんた・まりあ |
金子博子 |
有本芳水 |
草川 信 |
※ほかに「東支那海」「御朱印船ぶし」「南進倭寇の唄」、佐世保の「軍港娘」など。
●主な出来事 |
1月早々、東条英機陸軍大臣が「戦陣訓」を発表、将兵だけなく国民にも訓示を奨励、「戦陣訓の歌」も2社からレコードを発売。「そうだその意気」「出せ一億の底力」「進め一億火の玉だ」なども相次ぎました。
そして12月8日、日本軍はハワイ真珠湾を奇襲、マレー半島に上陸、米英両国に宣戦を布告して太平洋戦争に突入します。
歌は戦時歌謡のほか「新妻鏡」「湖畔の宿」「めんこい仔馬」などヒット。長崎ものは時局を反映して東シナ海を舞台にした歌が目立ちました。
|
【昭和17年(1942)】 全3曲から1曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
7 |
じゃがたら文 |
波岡惣一郎、藤原亮子 |
佐伯孝夫 |
島口駒夫 |
※ほかに、東シナ海がらみの「御朱印船」、玄界灘の「月の玄海」が出ています。
●主な出来事 |
日本軍はマニラ、シンガポール、コレヒドール島を占領しますが、6月のミッドウエー海戦で空母4隻を失い戦局の転機となります。銃後では塩、味噌、醤油が切符制配給となり、国民生活は“欲しがりません勝つまでは”の流行語の下で欠乏生活が深刻化します。
長崎では長崎日日、長崎民友、軍港(佐世保)、島原の4新聞社が強制統合され「長崎日報」で発足。5月20日戦艦「武蔵」が出港しています。
歌は「空の神兵」「月月火水木金金」や「南から南から」「南の花嫁さん」など。長崎の歌は3曲どまりでした。
|
【昭和18年(1943)】 全3曲から2曲
| No. |
月 |
曲 名 |
歌 手 |
作 詞 |
作 曲 |
| 1 |
3 |
ジャワの夕月 |
灰田勝彦 |
佐伯孝夫 |
佐々木俊一 |
| 2 |
4 |
殉国の歌 |
東海林太郎 |
大高ひさを |
松平信博 |
※ほかに「「平戸の歌」が出ています。
●主な出来事 |
日本軍は2月のガタルカナル島撤退、アッツ島日本軍全滅など重大な局面を迎え、12月には学徒出陣も行われます。ジャズ・レコードと1,000曲の米英曲は禁止、野球用語も英語の使用を禁止しました。
長崎では金属や米英製蓄音器の回収が始まり、長崎くんちの奉納踊りは中止。10月には日華連絡船「上海丸」が衝突事故で沈没しました。
歌は「加藤隼戦闘隊」「若鷲の歌」「お使いは自転車にのって」などが歌われましたが、さすがに低調でした。
|
【昭和19年(1944)】 0曲
●主な出来事 |
1月に女子挺身隊が結成されたほか、8月には国民総武装が決まり、竹やり訓練も始まります。しかし、サイパン、テニヤン、グアムの日本軍は全滅。10月に海軍の神風特別攻撃隊の攻撃が始まりますが、同24日には長崎で建造された戦艦「武蔵」もレイテ沖海戦で沈没します。
長崎では4月に中学校に学徒動員の指令が下り、三菱など主要生産部門に配置されます。8月11日、米軍のB29爆撃機が初めて長崎を空襲、6月から厳重な灯火管制に入ります。
歌は「特幹の歌」「轟沈」「勝利の日まで」など。長崎の歌は皆無でした。
|
【昭和20年(1945)8月まで】 0曲
●主な出来事 |
1月に大本営本土決戦の体制が決まりますが、4月には米軍が沖縄に上陸、5月ドイツが無条件降伏。東京大空襲の後、広島、長崎に原爆が投下され、8月15日天皇の終戦詔書の放送があり、終戦となります。
長崎では相次ぐ空襲の後、原爆投下で死者73,884人、重軽傷者74,909人をはじめ多くの市民が被災、惨憺たる状況の中で終戦を迎えます。
歌は「お山の杉の子」「神風特別攻撃隊」程度。長崎ものは皆無でした。
|
【もどる】
|
| |