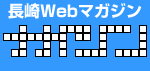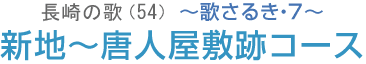|
 |

ランタンフェスティバルのメーン会場
としても賑わう中国風の「湊公園」
|
長崎には中国から様々な文化がもたらされましたが、音楽の分野では明楽(みんがく)と清楽(しんがく)があります。明楽が伝えられたのは唐人屋敷が出来る20年前の寛文6年(1666)のことでした。
文化文政年間(1804〜1829)になって長崎で清楽が盛んになり、次第に明楽・清楽を折衷した新音楽・明清楽(みんしんがく)が形成されます。その代表曲が「九連環(きゅうれんかん)」で、この旋律を基にした「かんかんのう」や「梅ヶ枝節」など多くの替え歌が幕末から明治、大正、昭和にかけて流行し、日本の流行歌謡に大きな影響を与えました。(「明清楽『九連環』の軌跡」) |
ここでは、バックナンバー「“長崎の中国”を歌う」で紹介できなかった歌の中から、中国船や中国人、中華街を取り入れた歌を年代順に紹介します。
なお、新地中華街にちなんだ歌“チャンポンの歌”はバックナンバー「長崎の食べ物賛歌」と「長崎言葉の歌(下)」で紹介しています。 |
1.「唐人船」
(昭和16年=1941、松坂直美・作詞、佐渡暁夫・作曲、三根耕一・歌) |
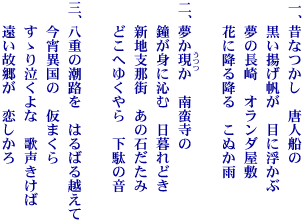 |
長崎に中国の船“唐船(とうせん)”が最初に来航したのは、約440年前の永禄5年(1562)のことでした。場所は港外の戸町浦(今の深堀町付近)だったそうです。
この歌は、ポルトガルやオランダ、中国と貿易をしていた鎖国時代の、長崎の賑やかな様子を描写しています。 |
“南蛮寺(教会)”の鐘の音が流れる新地中華街の石畳を歩く人の下駄のひびきが、夕方の静かな町の様子が感じられます。
作詞の松坂直美(まつざか・なおみ)は壱岐の出身。戦後ヒットした「緑の牧場」や「楽しいハイキング」「名月佐太郎笠」なども作詞しています。
吹き込んだ三根耕一(みね・こういち)はディック・ミネの別名(本名は三根徳一)です。「三根耕一」は昭和13年から短期間使った後、昭和15年には内務省からの指示で終戦まで使い、戦後に「ディック・ミネ」に戻りました。
長崎の歌は、戦後まもなく、映画「地獄の顔」に挿入された「長崎エレジー」や「夜霧のブルース」も歌っています。
|

明末清初期の中国船を復元した
「飛帆(フェイファン)」=出島岸壁で
|
2.「唐人夜船」
(昭和25年=1950、吉川静夫・作詞、吉田 正・作曲、竹山逸郎・歌) |
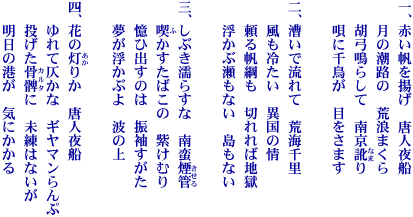 |
昔は中国からの船のほかに、ベトナムやタイ方面からやってくる船も含めて“唐船”や“唐人船”と呼んでいました。初めは悲壮な気持ちで荒海を越えて来ていたでしょうが、次第に長崎に溶け込み市中に住む人も多くなります。
長崎は地理的にも中国に近く、同じ東洋人。キリスト教徒でもなく鎖国時代でも中国人の来航は寛大な態度で迎えられ、長崎市民と次第につながりを深めていきます。
この歌は荒海を越えてやってきた唐人船と、異国の夜を過ごす乗組員の心を歌ったもので、作詞は青江三奈さんの「長崎ブルース」を書いた吉川静夫。作曲は当時ベテランの吉田正。歌も当時「泪の乾杯」「熱き泪を」「流れの船唄」などで人気のあった竹山逸郎(たけやま・いつろう)でした。 |

新地中華街の中心に建つ
「新地蔵跡」の石碑
|

館内町の上り口に建つ
「唐人屋敷跡」の石碑 |
3.三条町子の「長崎夜曲」
(昭和25年=1950、西岡水朗・作詞、利根一郎・作曲、三条町子・歌
) |
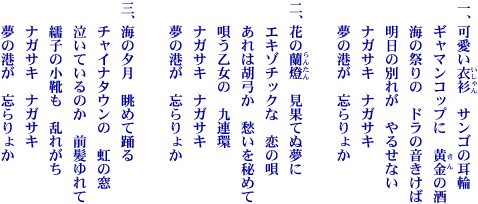 |
チャイナタウンの華やかな賑わいと、可愛いクーニャン(中国娘)の恋人との別れの哀愁を歌っています。 |
長崎出身の作詞家、西岡水朗(にしおか・すいろう)の作品ですが、このころの水朗は結核を病み、娘の嫁ぎ先・伊東市に転地療養していました。
この作品は療養先で書いたのか、それ以前、再起を目指して疎開先の秋田から東京に戻ったころの作品なのかは分かりませんが、「ギャマンコップに黄金の酒」や「花の蘭燈」など、水朗らしいエキゾチックな描写が多く見られます。
歌っている三条町子(さんじょう・まちこ)は昭和23年に宮野信子でデビュー。三条町子に改名して24年に吹き込んだ「かりそめの恋」がヒットしました。声の質から悲しい歌が多かったようですが、この歌は芯のある声で歯切れ良く歌っています。
|

独特のムードで観光客に人気の
新地中華街 |
|