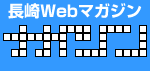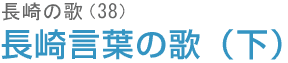1.「九州よかとこ」
(昭和53年=1978、星野哲郎・作詞、安藤実親・作曲、水前寺清子・歌) |
 |
|
 |
 |
“九州はよかとこ、おいでなはまっせ(九州は良い所、いらっしゃいませ)”と呼びかける観光ソングです。九州の歌だけに、熊本出身の水前寺清子(すいぜんじきよこ)さんも勇壮に軽快に、そしてコミカルに歌い上げています。
1番の「いっぺんきんしゃい」は長崎県の北部地方でも使われ、「一度来ませんか」の意味ですが、長崎市内では「いっぺんきまっせ」。また「よりんしゃい」も「寄りまっせ」となります。
2番の長崎言葉「おいでなはまっせ」は「おいでまっせ」(いらっしゃいませんか)の丁寧語です。「なは」を挟むことで、温かさと奥ゆかしさを感じさせますが、最近はあまり聞かれなくなりました。
この歌は九州各地で人気を集め、このレコードの後、3年後の56年には沢竜二(さわりゅうじ)さんが吹き込み、62年には水前寺清子さんも再び「オアシス音頭」とのカップリングでレコードを出しています。
|

「九州よかとこ」のレコード表紙 |
|
2.「凧(はた)あげ音頭」
(昭和54年=1979、出島ひろし・作詞、深町一朗・作曲、市川勝海・歌) |
|
 |
 |
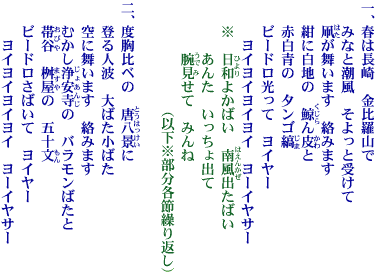 |

「凧(はた)あげ音頭」のレコード表紙
|
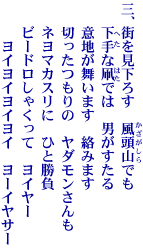 |
「九州焼酎音頭」の片面に収録された歌です。
「凧(たこ)」を長崎では「ハタ」と呼びますが、そのハタ揚げは長崎の春の名物行事です(バックナンバー30「長崎ぶらぶら節」(上)参照)。ハタ揚げに熱中する人々の様子を、長崎言葉の囃子を絡ませて面白く展開した歌です。
「ビードロ」はガラスの粉末を糊でまぶした糸のことで、この糸で相手の糸を空中で切り合います。3番の「ヤダモン」は相手の糸を切るため竿の先に付けたトゲのある木の枝、その枝を持った人、「ネヨマカスリ」は切られて落ちてきたヨマ(糸)を枝に絡めて奪い取ること。
歌詞の※印部分は「日和は良いですよ、南風も出ましたよ、あなた、ひとつ出て行って、腕を見せてみなさいよ」という意味です。
腕に自慢の亭主をハタ合戦に送り出す妻の強い期待が感じられます。
この種の歌には、やはり方言は欠かせないようです。 |
|
3.「雲仙ながし踊り」
(昭和55年=1980、出島ひろし・作詞、深町一朗・作曲、市川勝海・歌) |
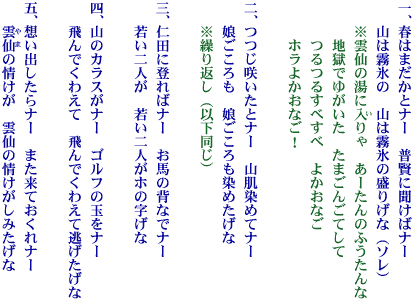 |
|
 |
 |
雲仙観光協会から作詞の依頼を受けた長崎在住の出島ひろしさんは島原出身でもあり、島原言葉の妙味を大胆に取り入れています。
各節にある語尾の「げな」は「〜だそうだ」の意味で、島原地方ではよく使われます。「ゲナゲナ話(ばなし)ゃ うそゲナ」という揶揄(やゆ)言葉が島原の子供たちの間にはやったこともありました。
歌詞の※印の囃子は「雲仙の温泉に入ると、あなたの頬(ほお)は地獄でゆでた卵のように、ツルツル、スベスベ…ほらこの通り、いい女になりますよ」という意味。「あたん」は「あんた」「あなた」、「ふーたん」は「頬」のこと。
島原言葉には独特のイントネーションがあり、その抑揚で聴く囃子はこの歌の聴きどころでもあります。
うちわを手にした浴衣姿のご婦人たちが温泉街に繰り出すあでやかな踊りは、夏のイベント「まつり雲仙」の定番として、今も人気を集めています。
|
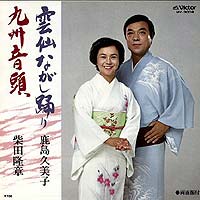
「雲仙ながし踊り」のレコード表紙 |

「まつり雲仙」の定番となっている「雲仙ながし踊り」のパレード |
|
4.「どげんしたとねBaby!」
(昭和56年=1981、田中昌之・作詞、作曲、クリスタルキング・歌) |
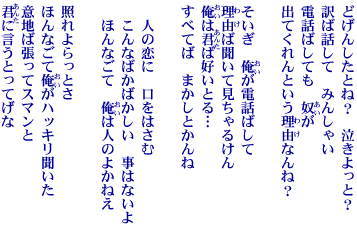 |
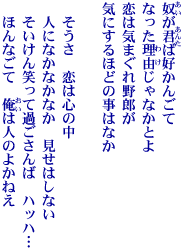
|
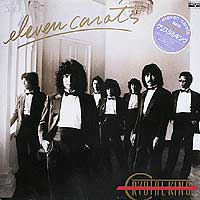
「どげんしたとね Baby」を
収録したLPレコードの表紙 |
クリスタルキングは4人の長崎県出身者を含む7人組のグループです。佐世保の米軍キャンプなどで活躍、ヤマハのポプコンでの入賞を皮切りに、各地のコンサートで実績を重ね、昭和54年(1979)にレコード界入りして、いきなり「大都会」を大ヒットさせました。
「どげんしたとね Baby!」は彼らのサードアルバムに収録した風変わりな曲。
メンバーの田中昌之(たなかまさゆき)さんの作詞、作曲で、佐世保のお人好しの友人をモデルにしたというコミカル・ポップスですが、九州各地の方言でまとめています。
漢字に方言のふりがなが付いているので、おおよその意味は理解できそうですが、それ以外の部分を説明しますと…。
*どげんしたとね⇒どうしたの *泣きよっと?⇒泣いているの? *みんしゃい⇒みなさい *そいぎ⇒それなら *見ちゃるけん⇒見てあげるから *ほんなごて⇒ほんとうに *照れよらっとさ⇒照れているのさ *言うとってげな⇒言っておいてだとさ *好かんごて⇒好かないように *そいけん⇒そうだから |
|
 |
 |
5.「好いと」
(平成9年=1997、佐田玲子・作詞・作曲・歌) |
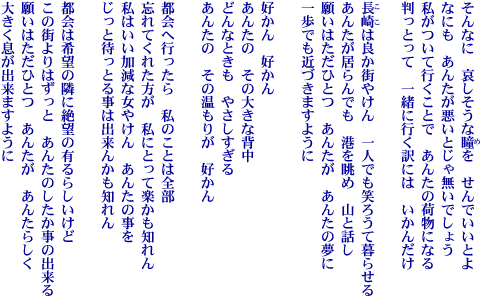 |

|

「好いと」のCD表紙 |
さだまさしさんの妹、佐田玲子さんが「好いと」(好きです)と「好かん」(嫌い)の2つの長崎弁を温かく織り込んで歌っています。
今の若い人たちも日常会話で使っている「やけん」(…だから)、「言わんけん」(言わないから)ていどの軽い長崎言葉ですが、地元出身らしく、長崎言葉の持つ独特のイントネーションを柔らかく使っているので、聴く人にもほのぼのとした優しい語りかけとなって届きます。 |
|
 |
 |
 |
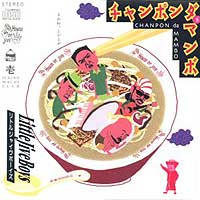
「チャンポンダマンボ」のCD表紙 |
長崎言葉を取り入れた歌の最新盤です。
藤井康一さん率いる4人編成のバンド、リトルジャイヴボーイズはジャズの日本語アレンジ、昭和歌謡、ハワイアン、サンバなど幅広い音楽に挑戦していますが、この歌は長崎名物チャンポンを取り上げた長崎人にとってはたまらない歌です。
金太郎楽団の「チャンポン」(バックナンバー13「長崎の食べ物賛歌」参照)のように、チャンポンの作り方、レシピも歌っていますが、金太郎楽団とはひと味違った、軽快なマンボの風のリズムに聴く人を乗せてしまいます。
また「良歌酔過隊(よかよかたい)」による「よかよか!」などの長崎弁コーラスを挟み、さらに歌詞としては書かれていませんが、次のような長崎言葉の早口掛け合いが笑いを誘います。
「ほんなこて いっちょん よかことのなかごたるですね! ハイ」(本当に一つも良いことは無いようですね!)
「終わってよかですか」(終わっていいですか?)
「でけん でけん!」(だめだめ)
「終わってよかですか」
「でけん でけん!もちっと しなっせー」(だめだめ、もう少し続けて下さい) |
|