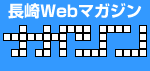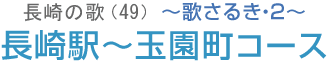|
 |

本蓮寺の広くて長い階段
|

本蓮寺に残る「南蛮井戸」
(柵の向うに蓋が被せてある) |
|
(4)福済寺 |
本蓮寺の隣には巨大な観音像が建つ福済寺があります。崇福寺、興福寺、聖福寺と共に“長崎四福寺”といわれる黄檗宗の唐寺です。
寛永5年(1628)、唐僧・覚悔が弟子を伴い長崎に渡来し、現在地の岩原郷に航海の神様・媽祖聖母を祀ったのが起源とされ、キリシタン禁制の取り締まりが厳しくなった際、中国人たちがキリシタン教徒でないことを証明するために建立した寺院の一つです。
建造物は戦前、国宝に指定されていましたが、原爆によって全焼。昭和54年(1979)、原爆被災者、戦没者の慰霊と平和祈念のために立てられた白銀色に輝く観音立像(万国霊廟長崎観音)をシンボルに、近代的寺院として生まれ変わりました。観音像は高さ34メートル、重さ35トンあります。
これも歌には出ませんが、散策の参考に。
|

福済寺に建つ長崎観音 |
|
(5)聖福寺の「じゃがたらお春の碑」
キリスト教の禁制にはいろいろな弾圧がありましたが、外国人と結婚した日本人女性と混血児たちの海外追放も大きな出来事でした。流された混血児たちが故国恋しさに、肉親や友だちに送った手紙を“じゃがたら文”と称しています。
“じゃがたらお春”は寛永16年(1639)、ジャガタラ(現在のジャカルタ)に流された混血児の中にいた14歳の少女“お春”のことです。 |
長崎市筑後町の子供だったことから、近くの玉園町にある聖福寺の境内に「じゃがたらお春の碑」が建っており、歌人、吉井勇(よしい・いさむ)の「長崎の鶯は鳴くいまもなほ じゃがたら文のお春あはれと」の歌が言語学者、新村出(しんむら・いずる)の書で刻まれています。
聖福寺は前述の福済寺からさらに東に200メートルほど歩いたところにあり、歌碑は境内の左手に建っています。誰が植えたか、秋には彼岸花(曼珠沙華)が伸びて赤い花を開きます。
歌では“じゃがたらお春”と“じゃがたら文”が歌われています。
|

聖福寺の「じゃがたらお春の碑」 |
| お春を歌った代表曲は「長崎物語」(「禁教の悲劇を歌う」)です。ほかにも“じゃがたら文”をテーマにした歌が数多くありますが、ここでは「踏絵」の片面に入った「じゃがたら文」を紹介します。 |
4.「じゃがたら文」
(昭和12年=1937、大木惇夫・作詞、阿部 武雄・作曲、関 種子・歌) |
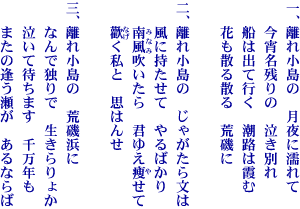 |