コラム 長崎が舞台の小説を読んでみた
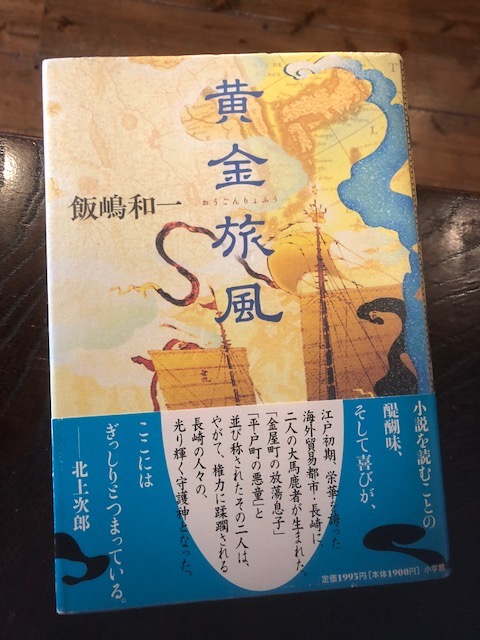
第2回 飯嶋和一の『黄金旅風』~舞台は朱印船が行き交っていた頃の長崎
「その岬は、爪先を伸ばした足を横から見た形に似ていた」
飯嶋和一さんが平成16年に発表した『黄金旅風』は、こんな一節から始まります。足指の部分にあたる大波止は「外国船」専用の船着場。踵(かかと)の部分「船津町」の河口は「国内船」の船着場であるという説明のあと、船津町から中国式のジャンク船2隻が出港するところから、いよいよ物語が本格的に始まります。
「船艫(ふなとも)の舵(かじ)受けの上には、『丸に平』を墨染めにした白旗がたなびき、その二隻が長崎の外町を支配する代官でもあり、朱印船貿易家として名高い末次平蔵政直の所有船であることを示していた」 (『黄金旅風』12頁から抜粋)
歴史用語が3つ出てきました。「長崎代官」「朱印船貿易家」「末次平蔵」です。
「代官」とは文字通り「主君を代行して官職を遂行する人」のこと。初代の長崎代官は、豊臣秀吉に任命された「鍋島飛騨守直茂(なべしまひだのかみなおしげ)」。2代目の代官は「村山等安(むらやまとうあん)」。そして3代目の代官が「末次平蔵」です。長崎を取り仕切る行政のトップは「長崎奉行」。その下に地役人の筆頭として、内町(うちまち/中心の24町)を管理する「町年寄(まちどしより)」。外町(そとまち/内町以外の町)と郷地を管理する「長崎代官」がいました。
朱印とは、秀吉が与えた「海外渡航許可書」のことです。秀吉亡き後は、徳川家に引き継がれ発行されました。この朱印を携えた船で海外貿易を行う者が「朱印船貿易家」です。本人自ら朱印船に乗る場合もありますが、自分はオーナーとして日本に残り、代行者が船に乗るケースが多かったようです。末次平蔵も船大将を濱田彌兵衛(はまだ やひょうえ)に任せていました。主な交易先は現在のベトナムにあたる交趾(コーチ)、東京(トンキン)、安南(アンナン)や、現在のフィリピンにあたる呂宋(ルソン)、現在のタイにあたる暹羅(シャム)などの東南アジアの国々です。
長崎の末次家は長崎開港の頃、博多商人だった末次興善(こうぜん)が移住してきたことにはじまります。朱印船貿易で財をなした興善は、町を開拓しました。それが「興善町」です。興善と一緒に移住してきた息子「政直(まさなお)」が末次平蔵の初代となりました。政直はそれまで金屋町の乙名(おとな)を務めていましたが、2代目代官の村山等安を告発し失脚させ、3代目代官の地位を手に入れました。以降、代官の職と末次平蔵の名は3代に渡って引き継がれていきました。2代目が「茂貞(しげさだ)」、3代目が「茂房(しげふさ)」、4代目が「茂朝(しげとも)」です。しかし4代目の茂朝の時、使用人がカンボジアで密貿易をしていることが発覚。茂朝は隠岐へ流罪、家族も壱岐に流され末次家は滅亡しました。
『黄金旅風』の主人公は、2代目末次平蔵の茂貞。主に長崎を舞台に、寛永5年(1628)から寛永10年(1633)までの約5年間に起こった歴史的事件を独自の解釈で描いた長編歴史小説です。この5年という区切りは、「タイオワン事件」が起こってから決着するまでの期間。この歴史的大事件を軸にして物語が展開して行きます。

<日蘭貿易の始まり~タイオワンにゼーランディア城建築まで>
日本とオランダとの出会いは、1600年のリーフデ号漂着に始まりました。110名の乗組員の内、生存者はわずか24名だったといいます。1605年、徳川家康は生存者の2名に渡航許可証を与えました。5年後、オラニエ公の親書を持ったオランダ船2隻が平戸に入港。オランダ人商人は家康と会見し「オランダ船は日本国内のどの港でも貿易をおこなってよい」という朱印状を手に入れたのです。
オランダ人はさっそく平戸に商館を置いて貿易を開始しました。初代商館長はヤックス・スペックス。ところが、日蘭貿易はオランダ人が思っていたほどの利益が上がりません。オランダ船の入港が不規則な上に、イギリス人やポルトガル人商人と競合していたからです。日本との貿易で最も利益を上げる商品は、中国の生糸と絹織物。最大のライバルのポルトガルを出し抜くには、これらの商品を確保するしかありません。そこでオランダは貿易拠点を確保するべく、ポルトガルの商館があるマカオを攻撃しましたが失敗。仕方なく台湾島の西方にある澎湖島(ぼうことう)に城を築きました。これに怒った中国と戦争状態に陥りますが「澎湖島の要塞を破壊して、台湾島に移ってくれれば、その地での貿易を認める」という、有利な休戦条約を結ぶことに成功。1623年、台南の安平(アンピン)にゼーランディア城を建て、この地を「タイオワン」と名付けました。
さて、せっかく手に入れた貿易拠点の台湾ですが、既にここでは日本人と中国人との間で取引が行われていました。1624年、タイオワンの長官に就任したマルティヌス・ソンクは、台湾からの輸出品に10%の関税をかけ日本人の閉め出しを計ります。「こっちは、オランダ人より前からここで貿易しているのだから」と関税の支払いを拒否した日本人に対して、ソンクは既に彼らが買い入れていた生糸を押収するなど、さらなる強硬策に出ました。
<平蔵vsノイツ~タイオワン事件に到るまで>
翌1626年、京都の朱印船貿易家の平野藤次郎と末次平蔵(初代の直政)に台湾行きの朱印状が与えられ、合わせて30万デュカット(銀約3000貫目)の大金を持ってタイオワンに行きました。ところが約束していた商品が中国から届いていなかったため、船大将の濱田彌兵衛は自ら中国は商品を受け取りに行こうとして、オランダからジャンク船を借りようとしましたが、断られてしまいます。空しくタイオワンで年を越した彌兵衛。帰りの船に商品は積めませんでしたが、代わりに16人のゲストを乗船させました。タイオワンの先住民たちです。16人を江戸に連れて行き、彼らにオランダ人の横暴さを訴えさせ、さらに「台湾島を将軍に捧げます」と言わせようというのです。タイオワンでの日本とオランダのトラブルについて、弁明するためにやって来たオランダの大使ピーテル・ノイツに対しても、平蔵は「大使と言っているが、ノイツは東インド会社のいち商人であって、オランダ国王から正式に派遣されてきたわけではないから、将軍に会わせるべきではない」と閣老に訴え、謁見を阻止。ノイツは怒り心頭でタイオワンに帰って行きました。
『黄金旅風』の冒頭、船津町から出航する末次の船には、先述した16人の先住民が島に帰るために乗船していました。タイオワンに着くと同時に16人はノイツによって拘束。平蔵を恨むノイツVS彌兵衛の「タイオワン事件」が勃発するのです。
<本編とは直接関係のない第3章>
『黄金旅風』は、タイオワン事件を発端にした利権絡みの権力闘争に、主人公の末次平蔵茂貞が巻き込まれるかたちで展開していく歴史小説です。ところが第3章では、主人公が突如として鋳物師の真三郎に交代します。真三郎は元キリシタンで、茂貞はセミナリオ時代の先輩ですが、直接的には関わりません。同じ時代に同じ場所で起こった別の話。まるで、違う小説が挿入されている様です。飯島和一さんがこのキリシタンをテーマにしたサイドストーリーを描いたのは、当時の長崎の持つ特殊性を浮き彫りにしたかったからではないでしょうか。
<オランダ人の手記に見るリアル末次平蔵>
クーンラート・クラメールの日記に、末次平蔵直政の衝撃的な最期が記されていました。「長崎で広く知られ、語られている話」として、次のように書かれています。
「彼の生涯の最後に彼は狂気となり、自分の罪を懺悔(ざんげ)し、閣老、平戸侯、その他大勢の高官を糾弾しつつ告白を始めた。(中略)これらの高官たちこそ、彼の破滅と、彼が行なった悪事の原因であり、彼はただこの手段として用いられただけで、このため今神にひどく罰せられている、と甚(はなはだ)しくかきくどいた。江戸の代官達に、この邪悪な平蔵の狂気の噂が伝わると、彼らは平蔵を、発狂したという理由で、牢獄に幽閉させた。」(平戸オランダ商館日記 第1巻363頁から抜粋)
平蔵は、大名や一部の閣老たちと深く結びついていました。松平正綱、永井尚政、井上正就(まさなり)や平戸の松浦氏らは、密かに平蔵船に投資して利益をあげていたと考えられています。平蔵は晩年になって、閣老たちが自分を通じて密貿易をしていたことを告白し始めました。閣老が貿易に介入、従事することは禁じられていましたから、バレたら切腹ものです。彼らは平蔵を発狂したとして牢獄に押し込み「皇帝の家臣により、刀で袈裟がけに斬られた」という映画の様な話なのですが、実際のところはどうだったのでしょうか。
余談ですが、平蔵に投資したと言われる井上正就の弟は、遠藤周作『沈黙』にも登場する宗門奉行の井上筑後守政重。マーティン・スコセッシの映画ではイッセイ尾形さんが演じていました。
クラメールは、2代目平蔵こと茂貞についてもこう記しています。
「平蔵の息子があまり売春婦共と放蕩したり、また容易に想像のつく様に、これに類する他の悪事にも手を出していたために、平蔵はこの十二、三年間、息子と逢って話そうとはしなかった。彼は友人のとりなしで、平蔵の死ぬ前に江戸に呼ばれ、ここで父の官職と世襲の領地を、遺言状により全部譲り受けた。」(平戸オランダ商館日記 第1輯363頁から抜粋)
『黄金旅風』の茂貞像とは違いますが、小説家はこういった第一次資料から人物像を膨らませて行くのでしょう。
『黄金旅風』というタイトルは、物語に出てくる「金の繭玉」に由来しています。クーンラート・クラーメルの日記には「黄金の羅紗」に関する記述が見られました。また、物語で茂貞と敵対する長崎奉行の竹中采女についての生々しい記述も記されています。
「実際には、このような金色羅紗が日本に来て彼等に渡されたことは、未だないため、我々がその値段にふさわしい金額を要求すれば、采女殿の非常な憎しみを受けることは容易にあり得る。何しろ彼は甚だ金銭慾が強く、我々に面倒をかけることをやめようとしない」(平戸オランダ商館日記 第1輯360頁から抜粋)
<『黄金旅風』を歩く>
1勝山町の末次平蔵宅跡(長崎市立桜町小学校)2本博多町の長崎奉行所跡(NTT長崎支店)
3船津町の船着場(恵美須町の瓊ノ浦公園)
4末次平蔵茂貞の墓(春徳寺)
【参考文献】
『平戸オランダ商館日記 第一~三輯』永積洋子(岩波書店/1969)
『平戸オランダ商館日記 第四輯』永積洋子(岩波書店/1970)
『朱印船』永積洋子(吉川弘文館/2001)
『長崎史の実像』外山幹夫(長崎文献社/2013)
『長崎町づくし』(長崎文献社/1986)
『長崎地役人総覧』籏先好紀(長崎文献社/2012)



