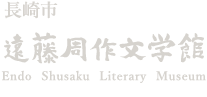本文
第10回文学講座(H22.3.13)
題目 戦時下の信教の自由――遠藤周作の場合
講師 徳永達哉氏(九州国際大学)
平成22年3月13日、憲法学(人権・表現の自由・政教分離)をご専門とされる徳永達哉先生をお迎えし、文学講座を催しました。
先生は、大日本帝国憲法下の信教の自由について、信教の自由は謳われてはいたものの「臣民としての義務に背かない限り」という制限付きであったとご解説くださいました。
戦時中大学生だった遠藤は、天皇を「現人神」とする戦時下において、敵性宗教であるキリスト教を信仰する心の葛藤を、小説家となってから『黄色い人』『女の一生・第二部』『薔薇の館』などで描いています。
先生によれば、戦時下において「キリスト教徒である」ということは、敵性宗教を信仰しているということから派生して「欧米のスパイなのではないか」もしくは「反戦思想の持ち主」として治安維持法違反容疑をかけられ、それをもってして「臣民としての義務に背いた」とみなされ、容易に官憲に監視される状況を生むこととなったということです。また当時の記録によれば、「キリスト教徒である」ということが逮捕の根拠となることはなく、「スパイである」とか「反戦思想の持ち主」という容疑で逮捕されることがほとんどであったそうです。
遠藤自身が大学生活を送った戦時下とは、こうした複雑な思想の監視システムの下にあったということを具体的に解説してくださいました。