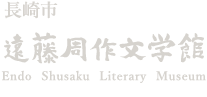本文
第9回文学講座(H21.12.21)
題目 『哀歌』を読む
講師 下野孝文氏(長崎県立大学)
平成21年12月21日、『沈黙』への前奏曲となった短編集『哀歌』のなかから外海地区を模して描かれた短編「帰郷」の鑑賞を深める講座を開催しました。今回の講義は、『沈黙』上梓後に執筆された作品における「父親像」のあり方を吟味することで進められました。遠藤文学の愛読者にとって、「母親像」というものはとてもなじみ深いものでありながら、その一方で「父親像」はあまり関心の対象とされてこなかったこともあり、新鮮な講座となりました。
作中における「亡父」は遠藤の実父をモデルとしていることは明らかですが、「亡父」同様に実父が「脂足であったか」「慎重で臆病な性格であったか」という部分については、実証できない部分です。ですが、この実証できない創作個所が、作品を読み解く重要な鍵となります。遠藤は昭和30年代から「おバカさん」などにおいてたびたび、実父を彷彿させる人物を「父」として登場させ描いてきました。遠藤が作品において描いた「父親像」の特徴は、『沈黙』以前は実父の出身地や勤め先といった社会的属性のみを借りて創り上げているのに対し、『沈黙』以後の作品においては遠藤とおぼしき小説家の「私」が「父」を憎むという激しい表現に変化していることです。この表現上の変化は、『沈黙』以後、「母なるもの」への思慕を顕著に表していく遠藤文学における「母」への思いと反比例するように存在し、短編「帰郷」における「遺伝的に脂足を持ち慎重で臆病な父方の先祖を持つ主人公・「私」」という作品の理解に深みを与えてくださいました。