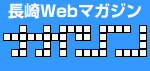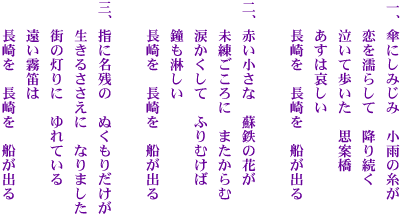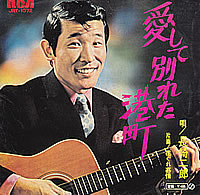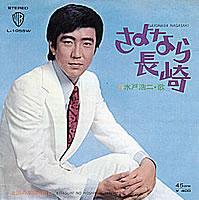| 長崎の歌には、都会で心に傷を負って放浪の旅に出た人が長崎にたどり着き、祈りの鐘の音と静かな街のたたずまい、人情にふれて心を癒される…というパターンがよく描かれています。そんな長崎にも未練心を抱きながら旅に出る“別れの歌”もあります。別れの形はさまざまですが、長崎らしい別れのパターンはどんなものか、発売順に拾ってみました。 |
| |
1.「さらば長崎」 |
| (昭和16年=1941、矢島寵児(やじま・ちょうじ)・作詞、利根一郎・作曲、小林千代子・歌 ) |
 |
 |
 |
朝霧が晴れていく長崎港を出る船の行く先は上海でしょうか。当時、長崎〜上海間に日華連絡船の長崎丸と上海丸が通っていました。昭和10年には日華連絡船で賑わう出島と長崎の魅力を歌った「長崎行進曲」(東海林太郎・歌)も出ています。
その日華連絡船は戦争とともに影が薄れ、昭和17年(1942)に長崎丸が伊王島沖で機雷に接触し沈没、翌18年には中国揚子江沖で上海丸が事故で沈没して日華連絡船は廃止されました。 |

帆船も寄港する今の長崎港 |
美しいソプラノで長崎の魅力を歌い上げた小林千代子は戦前流行した“覆面歌手”の第1号です。朝鮮民謡「アリラン」でデビューする際、黄金色の仮面を付けて現れ、話題を集めました。1年後「涙の渡り鳥」がヒットして小林千代子の名を決定的なものにします。
戦後は昭和25年にクラシック歌手に転向して、芸名を小林伸江に改名し「小林伸江歌劇団」を結成。恩師のオペラ歌手、故三浦環を継いで「マダム・バタフライ」の公演を続けました。
昭和42年に「マダム・バタフライ世界コンクール」を創設、長崎にもたびたびやってきて、38年、グラバー邸に建立された三浦環像除幕の際は立像の前で「ある晴れた日に」を歌いました。 |
|
|