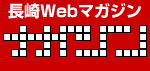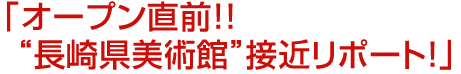Q.長崎の人は、よく新しいもの好きで飽きっぽいといわれますが、その反面自分達が誇れるものに関しては、とても肩入れする傾向があると思うのですが、ズバリ!長崎県美術館の他都市に誇れる部分ってどんなところでしょう?
逆に、最初は誇れないと思いますけどね。きれいな建物ができた、というぐらいのものでしょうね。でもそれが、文化的にみても芸術的にみても、よく考えられたプログラムとして、さっき言ったいろいろな人達に対応していて、そういう美術館が長く活動を続けられていくというのが、誇れることになっていくから、逆に飽きっぽいというよりは、最初は関れるものが少ないと思うんですよ。たぶん長崎の人達は関わりたいと思っていると思うんです。ペーロンにしたって、おくんちにしたってこれだけ長く続いているわけじゃないですか。ランタンにしたって育っている。
長崎の人達は関れるものがあるかないかで、随分姿勢が違ってくると思うんですよ。それでプログラム作ってボランティアを募集したら300人位の応募があって、85%、長崎の人ですから。そのネットワークを県中に広めたいんですよね。美術館がない所でも美術館を感じてもらえるようにしたいんですよ。だから、関わって誇れるものを造って欲しいんだけど、何を誇れるかっていうと、関わってその後は自分達が育てていく。何があるから長崎として誇りというんじゃなくて、自分が誇れるような、それに関わった人達1人1人が自分を誇れるような、美術館にしたいと思いますね。
財政的にはとても厳しく、運営予算を考えるとゼロからの出発なんですよね。
過激な言い方だけれども、僕は全部がゼロでもいいと思っているんですよね。全部がゼロなら、1日24時間全てがアイデアの宝庫になってくるわけですよ。考えて動かなきゃいけないから。そういう美術館を本当の意味で県民や市民が支えていくためには、どれだけでも人がいるわけですよ、人のアイデアがね。
内のアイデアと外のアイデアとが重なって、美術館が支えられているという関係が外に表現できたら「長崎はすごい」ってことになるわけですよね。それは、「きれいな建物を造った」「すごく有名な絵を持ってきた」というのとは僕はまた違う偉さがあると思いますね。現在、そういう形態のものは他都市にはないですね。皆さんに、様々な意見をバンバン入れてもらえるような館長箱を設けようかなとも思っています。(笑)
まずは、関わり方としてはボランティアや友の会ですよね。海外の美術館ではボランティアを養成して解説することも多いんですけどね。今回年間通じて13もの教養講座を準備してきたんです。やはり、お金を払えないけど、何らかの形で還元していくという形をとっていかないと、長く続いていかないんですよね。そして、次のステップ。プロフェッショナル・ボランティアといいう、プロ意識を持ったボランティアの育成をするんです。これが長いスパンで、美術館の力になっていくだけではなくて、次々と新しい人材を育成していくことによって、街の力、地域の力になっていく。美術館はそういう起爆剤にしたいですね。そして、観せるものはやっぱりいいものを出したい。今年度の展覧会で6つのうち4つはうちが皮切りでうちが考えたものなんですよ。ここを皮切りにここから発達して行く。そのプログラムの一つ一つがここで生まれたものだという感動があったら可愛がってもらえるんじゃないかというのはありますね。
新生“県美”にはいっぱいの刺激、感動、寛ぎ、出逢いが待ち受けているようだ。長崎県人の方は、まずはいち早く足を運び、自分達がどのように関れる場所であるのか接点を見つけてみよう。きっと楽しみがあふれているに違いない。だって新生“県美”は長崎県をまるごと吸収し、発信する皆が共有できる
“コミュニケーションーセンター”のようなものだから。そして、県美の今後の成長はワタシとアナタのアイデアにかかってもいる! また、注目の企画展、今年度のテーマは『長崎と西洋』。この長崎港を見渡せる新スポットに、長崎県の歴史と文化の薫りが、どこからともなく漂ってくる1年間になりそうだ。
|