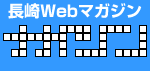1.「長崎育ち」
(昭和48年=1973、美輪明宏・作詞、作曲、歌) |
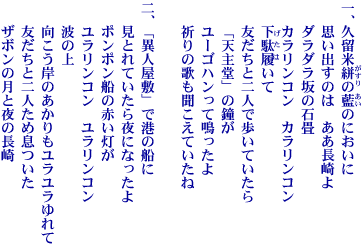 |
|
 |
 |
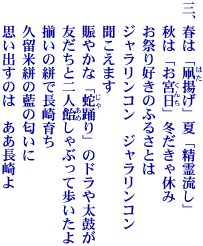
|

石だたみの坂道
(南山手のドンドン坂) |
長崎出身の俳優でシャンソン歌手、美輪明宏さんは昭和48年10月、ふるさとへの郷愁を詰め込んだ「長崎育ち」を作って吹き込み、LP「美輪明宏/華麗な世界」で発表しました。
下駄を履いて歩いた石だたみの坂道、夕べには天主堂の鐘が聞こえ、ポンポン船の赤いランプが港に揺れている…“紅顔の美少年”といわれた少年時代の美輪さんと、その時代の長崎の街がほうふつとしてよみがえります。
そして名物ハタ揚げ、精霊流し、くんちも歌った“ふるさと賛歌”です。 |
|
2.「長崎名物ぶし」
(昭和51年=1976、出島ひろし・作詞、村沢良介・作曲、市川勝海・歌) |
|
 |
 |
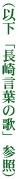  |
既にバックナンバー13「長崎の食べ物賛歌」、37「長崎言葉の歌(中)」で部分的に紹介済みですが、1番は名所、2番に長崎土産、3番に長崎の味、4番に長崎方言を面白く紹介した、文字通り“長崎名所名物の歌”なので、改めて登場させました。
一番の歌詞のうち、「館内(かんない)」は3番の歌詞にあるように、ちゃんぽん、皿うどんで有名な新地町の中華街に通じる中国文化・歴史を持つ町で、鎖国時代に唐人屋敷のあった地域です。町名も唐人館の内にあったことから付けられました。 |
「十善寺(じゅうぜんじ)」は、江戸時代、館内町・稲田町・中新町・十人町一帯を「十善寺村」と呼び、天保年間に長崎村の一部となって「十善寺郷」に。大正2年(1913)に館内町など町名が付けられた際、「十善寺郷」は消えましたが、長崎市民にとって“館内・十善寺”は愛着を感じる地名です。
館内町には土神堂や観音堂、天后堂など唐人屋敷の遺構が現存しているほか、古い石段や昔ながらの市場があり、中国文化と市民生活の香りが漂っており、思案橋〜丸山〜館内〜十善寺…は散策に欠かせないエリアでしょう。
|

土神堂(どじんどう)や市場が並び
下町風情たっぷりの十善寺地区の館内町 |
|
3.「ながさき踊り」
(昭和53年=1978、出島ひろし作詞、渡久地政信・作曲、金沢明子・歌) |
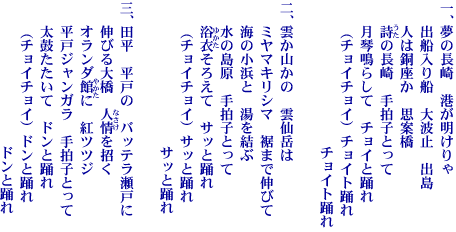 |
|
 |
 |

出船入り船でにぎわった往時を偲ばせる
長崎港の「帆船まつり」
|
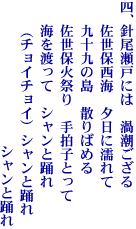 |
昭和50年代の特徴の一つに“民踊ブーム”があり、各社から民踊のレコードが出て、長崎民謡舞踊連盟も発足するほどでした。この歌のように、1つの歌詞に2通りの曲が付き、違う歌手が歌って競作する現象も見られました。
作詞は長崎の出島ひろしさん。偶然にこの作品(詞)の存在を知ったビクターとテイチクの各レコード担当者が持ち帰り、ビクター盤は渡久地政信さんが作曲、人気上昇中の金沢明子さんが歌い「ながさき踊り」で、テイチク盤は村沢良介さんが作曲、南高国見出身の市川勝海さんが歌って「長崎おどり」の題名で、昭和53年2月に同時発売となりました。
双方とも石橋輝興(いしばしてるおき)さんがそれぞれに振りを付け、石橋さんが指導する舞踊団体を中心に盆踊りなどで踊られました。
歌詞はビクター盤ですが、テイチク盤とほとんど同じで、長崎、島原、県北各地の名所を歌い上げたものです。 |
|
4.「もってこい長崎」
(昭和61年=1986、野村耕三・作詞、市川昭介・作曲、西岡はるみ・歌) |
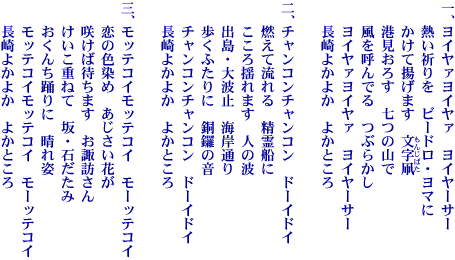 |
長崎の名物行事と名所をふんだんに取り入れた歌です(バックナンバー22「お盆と精霊流しの歌」参照)。1番にハタ揚げ、2番に精霊流し、3番に長崎くんち、4番には浦上の平和像も出ています。
ハタ揚げについては「名所名物の歌(上)」などでも触れているように、長崎の春の名物行事です。普通の凧揚げとちがって、相手のハタに絡ませて糸を切り合う競技もあり、ハタの種類もさまざまです。
糸(ヨマ)はガラス(ビードロ)の粉をまぶした「ビートロ・ヨマ」を使い、切り合います。それを「つぶらかし」と呼びますが、それが転じて、ハタ揚げに金を使いすぎて財産をつぶした人を“財産つぶし”という意味にも取られました。
「文字凧(もんじばた)」は桐に鳳凰、天下泰平、大吉などの文字の形を取り入れたハタの種類の一つです。
|
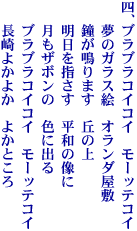 |

|
|
 |
 |
5.「長崎ごよみ」
(昭和62年=1987、石橋輝興・作詞、市川昭介・作曲、由岐ひろみ・歌) |
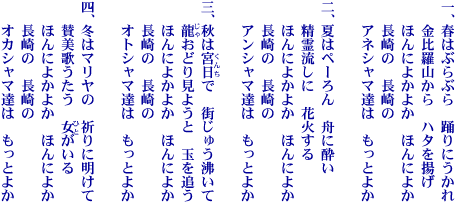 |
民謡舞踊研究家・石橋輝興さんが自ら作詞し、振り付けた舞踊のための歌です。
「ながさき踊り」の項で触れたように、“民踊ブーム”のころは、さまざまな歌が作られました。前項の「もってこい長崎」も同様で、その土地の名所名物が歌い込まれ、踊りを楽しみながら、ふるさとの魅力も見直す…という一挙両得の感もありました。
この歌も春のハタ揚げに始まり、夏のペーロン、精霊流し、秋のくんち、龍(じゃ)踊り、冬は祈りをテーマに、行事に熱中する長崎のアネシャマ(年上の女性)、アンシャマ(年上の男性)、オトシャマ(父親)、オカシャマ(母親)たちを紹介しています。 |

2番に歌われている夏の名物行事「ペーロン」
|
|
|
6.「しっぽくパラダイス」
(平成4年=1992、松原一成・作詞、大鋳武則・作曲、ZINM・歌) |
 |
 |
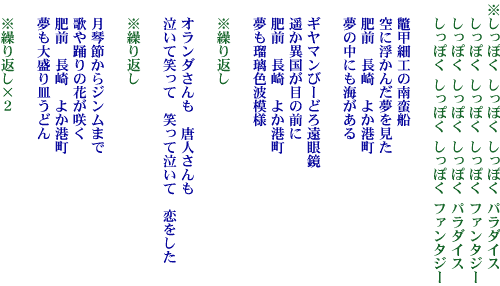 |
長崎をテーマにした歌にこだわり続けた長崎のグループ、ZINM(ジンム)のCDアルバム「長崎熱」にヒット曲「みんな長崎を愛してる」と共に収められた14曲の長崎の歌の1曲です。
長崎料理「卓袱(しっぽく)」をベースに、べっ甲細工、ギヤマン、ビードロ、月琴節、皿うどん…など、長崎名物を散りばめ、軽快なテンポで歌っています。
|

長崎名物料理の一つ「しっぽく」 |
|