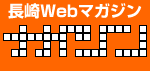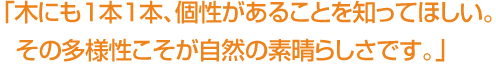まずは、樹木医の免許を取ったきっかけを教えてください。
久保田さん「僕は千葉大学の造園学科を卒業後、東京の造園会社に10年間勤めました。平成12年に長崎へ戻ってきたのですが、その頃、東京でお世話になった会社の人に「長崎は樹木医が少ない。もう少し増えた方がいいのではないか、受けてみてはどうか」と言われ、受験したんです。中央には免許を持っている人がたくさんいましたが、僕が受験した平成16年当時は、長崎は最下位に近かった。今でも県内の樹木医は11人しかいません。」
どんな試験を受けたのですか?
久保田さん「樹木や害虫、病害についてなど、基本的な知識を試す選択試験と、緑化や樹木、森林保護についての小論文が出ました。その問題文は面白かったですね。 例えば、『太平洋の孤島・イースター島は5世紀までは島全体が森林に覆われていたが、18世紀にヨーロッパ人が発見した時には、山はなく、そこにはモアイ像があるだけ。現地の人に聞くと、モアイは勝手に歩いてきたという。しかも、食べ物も粗末なものしかなく、島は人間が文明的な暮らしをする状況ではなかった。これを踏まえて、そこから得られる教訓を書きなさい』みたいな問題なんです。 」
|