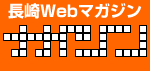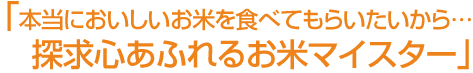お米マイスターとはどういうものですか? また、なぜその資格を取得しようと思ったのですか?
松尾さん「お米マイスターは平成14年度から始まった制度ですが、私はこのスタートの時に試験を受けて、資格を取得しました。お米マイスターの定義は『お米に関する幅広い知識を持ち、米の特性(品質特性、精米特性、ブレンド特性、炊飯特性)を見極めることができ、その米の最大の特長を活かした商品づくりを行い、その米の良さを消費者との対話を通じて伝えることができる者』となっています。私はこの仕事をやっている以上、自分の知識を確かめてみたいというのもあり、試験を受けました。」
お客様にすすめるときに心がけていることは何ですか?
松尾さん「お客様にすすめるときというよりも、仕入れの段階で心がけていることの方が大きいですね。私は必ず自分で買って食べて納得した米だけを販売するようにしています。やっぱり実際に食べてみて『これは、おいしくないな』というものもあるんですよ。そういう米は販売できませんよね。香り、味、甘み、ねばりなどを確認し、おいしいと思うものだけを売る、自信を持って売るということが大事だと思います。 これは、育った環境も関係しているかもしれませんね。私がこの店を継いでもう40年になります。小さい頃から、米に対する姿勢は他の家庭とは違うものがあったと思います。新しい米が入るたびに、食卓でこの店の初代でもある父と試食していましたからね。今は基本的には私が好きな県の米を取り寄せて試食をするのですが、その好きな県の米に辿り着くまでにも、たくさんの試食を重ねました。マイスターの資格の中には米の特性を見極めるという項目も入っていますが、それはコシヒカリやひとめぼれなどの品種を見極めるのではなく、いい米かどうかを見極めることを意味します。 もうすぐ新米の季節なので、またたくさんの米を試食して、みなさんにお届けしたいですね。 」
|