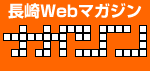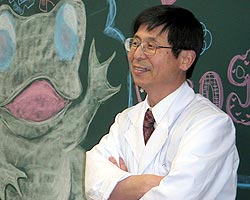身近にそのような自然の素晴らしさを感じる機会が少なくなっていると感じますが、昔と比べるとカエルの数も減少しているのでしょうか?
松尾さん「最近、カエルの姿を見なくなった、とか、カエルの鳴き声を聞かなくなった、と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。実際、山のカエルは多く生息しているのですが、水田や池にすむカエルは減少しています。
現在は水田自体が減少しているうえに、農業の機械化により、水を田植えの直前に入れて、必要がなくなると抜くという水田の乾田化が進んでいます。そのためにカエルの産卵場所や生息場所がなくなってきているのです。
2001年に発表された長崎県レッドデータブックによると、以前は水田に多く生息していたトノサマガエルや、冬場に水田や池に産卵するニホンアカガエルなど、4種のカエルが絶滅危惧類、準絶滅危惧種に指定されています。日本の水田のカエルを守るには、オタマジャクシが健康に育つことができる水田や低湿地に、一年中水がある状態をつくることが必要なのです。」
人間の生活様式の変化は自然にも大きな影響を与えているのですね…
それでは、今後の目標などがあれば聞かせてください。
松尾さん「よく何のために調べているのかと聞かれるのですが、好きだから仕様がない、と答えています。せっかく30年も調べてきたのだから、これからも長崎の野山を歩き回り、カエルとの出会いを楽しみたいと思っています。
両生類は移動手段がないために、島ごとに固有種が生息しています。島の多い長崎は研究者にとって理想的な場所なのです。今後も長崎にこだわって調査を続けていくつもりです。
また現在、調査対象は両生類から爬虫類、哺乳類へと拡がっていて、特に国の天然記念物ニホンヤマネの研究では全国にも知られるようになりました。いつか哺乳類についても本にまとめることができたらいいなと考えています。」
最後に、観光客、またはこれから長崎に移り住む方へ訪れて欲しい場所など具体的なアドバイスを。
|