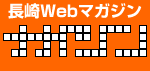|
16年前、伊良林地区から滑石地区に引越しをした。
伊良林地区は便利な所で、寺町通りを歩いて浜の町へ行くのも新大工市場へ行くのも10分程度。
「飴屋の幽霊」で知られる光源寺の裏手に我が借家はあった。
秋には若宮神社に出かけ、長い青竹が空中でゆらゆら揺れる中、狐の面をつけた男が曲芸を披露する、いわゆる「竹ン芸」が楽しみで早くからいい場所を確保したものだった。
長崎くんちのしゃぎりの音もよく聞こえ、ベランダから望遠鏡で諏訪神社の広馬場がよく見えた。
さらに中島川の川沿いはいい散歩コースであった。
便利な所だったのでよく人が集まる家だった。
とても気に入っていたにも関わらず子供の就学の折に滑石に越した。
この「滑石」にはみんなが一様に「エーッ、何で滑石なんかに?」と驚いた。
私の両親は金沢の出身で私は福岡の生まれである。だから友人達の反応には意外であった。
生粋の長崎生まれの彼女達からみれば「滑石」は長崎の中にカウントされないらしい。
私は何度も新しい我が家に彼女達を招待し、滑石がいかに整備された住みやすい町か認知を迫ったものである。
最近は友人も「なるほど、便利は便利だね」とは言うものの、頑として長崎とは駅から向こう側(南部)であるという認識は変えない。
そして私自身もいつの間にか諏訪神社のしゃぎりの音がすっかり遠のいてしまった。
近年我が家の守備範囲内に新しい名所ができた。
「あぐりの丘」と、ちょっと遠いけれど「遠藤周作文学館」。
どちらもそのロケーションがいい。
「あぐりの丘」は我が家から車で5分ちょっと。
最近は年配のグループのウォーキングコースとして人気がある。
私は怠け者だから車で走って中をぶらりぶらりと歩き回り、ソフトクリームを食べたり、コーヒーを飲んだりして2時間ほどを無為に過ごす。
これで気分が幾分リフレッシュできる。
|
遠藤周作については『沈黙』と、その他のユーモア小説の作者としてくらいしか知識がなかった。
と言っても『沈黙』は、読んだ当時深く深く感銘を受けたことを覚えている。
もともと外海という所が好きだったことと、遠方からやって来た友人達がぜひ行きたいというので4回ほど訪れた。
文学館の一部がほの暗く部屋の海に面した壁を細長くガラス張りで切ってある。
涙がでそうなほど蒼い海が切り取られてそこにある。
|

遠藤周作文学館 |
長崎生まれでもない遠藤周作が長崎を、特にこの外海の町を「心のふるさと」とした理由は何なのだろう。
幕末から明治にかけてのキリシタン迫害の折、多くのキリシタンや宣教師たちの祈りに応えてくれなかった神の「沈黙」、それでもなおかつ信仰を捨てなかった人々の生き様や叫びがここで聞こえてきたのだろうか。
何か見つけられるかもしれないと考え、私は帰り際500ページはある一冊の文庫本『女の一生・一部 キクの場合』を買った。
何げなく手に取ったものだったが面白く、哀しく一気に読んだ。
一般に長崎駅から北の方は大まかに浦上地域と言われ、かつて多くのキリシタン教徒がいた所とは聞いていたが、いわゆる「長崎」と言うのは今のJR長崎駅から南であることがはっきりとわかった。
路面電車の走っている宝町や目覚町の電停辺りは当時海で、この辺の海で採れた貝などの海産物を、西坂を越えて「長崎」に入り行商していた事がわかる。
駅から北の浦上は一部を除き「キリスト教徒」が多く居たらしい。
当然キリスト教は禁止されていたので「隠れキリシタン」と呼ばれている人達であった。
小説『女の一生・一部 キクの場合』はその隠れキリシタンである青年を愛した若い女性の短い一生の物語である。
当時建造中であった大浦天主堂の神父プティジャンや外海町で当時の町興しに貢献し、今なおド・ロ様と慕われているド・ロ神父も登場。
歴史的背景が正確に描写されており、「隠れキリシタン」を取り締まる奉行所や当時の実在の役人も現われてどこからどこまでが物語なのか区別がつかない。
禁制のキリスト教徒であると捕らえられ、むごい迫害を受ける男のためにあらゆる方法でそれを救い出そうとする「キク」。
キクにはキリスト教と言うものが理解できてはいなかった。
ただただ愛する男のためにその命までを注ぐ。
男が慕う女性、つまり「マリア」。
大浦天主堂のマリア像の前で「あんたなら救えるやろう」と言って命果てるのだ。
この部分はもちろん物語なのであろうが、今もそのマリア像は大浦天主堂にある。
そして今の山里や平野町にあたるのであろうか、当時、平野郷、上野郷と言われていた所に住んでいた多くの隠れキリシタンが、山間の道を西山から大浦へ抜け密かに天主堂を見上げたという。
その手をあわせる姿が目に浮かぶようであった。
現代の混雑する駅前から宝町、目覚町、浦上一帯をいつもいらいらしながら車を運転するのだが、本を読んでからは、車窓の右側の山間にふと目を走らせることが多くなった。
今の路面電車の走る道を歩けばなんてことはない距離だが、当時(明治の初め)、おそらくひとつの集落から集落まで道なき道であったに違いない。
そこから出て町(浜町周辺)へ行き、行商をして密かに大浦へ回ってくるだけで一日がかりだったであろう。
隠れキリシタンとプティジャン神父がハタ(凧)を上げて連絡を取り合うというくだりなど、ハタ揚げのさかんな長崎ならではの妙案である。
小説がぴったりと長崎の歴史と文化と地形にはまる。
史実とフィクションが見事に一体化するそんな長崎をもう一度歩き、読み、感じてみたいと思うこの頃だ。
森永 春乃さん
長崎大学経済学部講師。留学生専門の担当教官。アジアに感心を持っておられ、将来的には留学生であった教え子達を訪ねて各国を旅行するのが楽しみなのだとか。
|