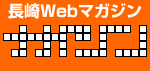|
長崎の坂動きだす三日かな 朗人
興福寺の山門を入り、本堂の方へ階段を登り切った所に句碑が建っています。
作者は俳誌「天為」の主宰で私の師である有馬朗人先生です。
当時文部大臣だった先生は、多忙の中をSPを随えて句碑開きに参加下さいました。
長崎に住み、長崎の句を詠み続けて三十有余年、私にとって長崎は、歴史的、風土的特徴がある場所や行事が多く、俳句の詠み手として興味は尽きません。
さてそれらを私の俳句と共に紹介して行きましょう。
寒明けの乾坤一に句碑成れり(興福寺)
全国の会員を迎え、長崎支部員一同の慶びは一入のものがありました。
長崎の春は、中国寺や唐人街の上元会(元宵祭)と共にやって来ます。
近年ランタン祭りとして大勢の観光客を呼んでいます。
朱蝋百 百の願ひの上元会(崇福寺)
春聨や支那饅頭の臍紅く(新地)
幕府の鎖国政策として、出島にはオランダ人を、唐人屋敷には中国人を収容し長崎港は江戸時代唯一の窓口として貿易港であったのです。
媽姐さまの春衣にのぞく赤い靴(天后堂)
羅の遊女出入りの出島橋(出島)
現在も外国船が優美な姿を横たえ、さまざまな船が行き交います。
なかでも夏のペーロンは市をあげての行事で圧巻です。
春燈を満載にして巨船泊つ(港)
ペーロンの龍あざやかに出を待てり(競渡)
さて外人墓地も長崎らしい所と言えましょう。
居留地で、或いは船員として亡くなった人々が、坂本町、稲佐、大浦の墓地に永久の眠りについています。
枯るる声きく望郷のロシア墓
蟷螂の斧あげ凍つる異人墓地
シーボルトが商館員として多くの弟子を育てていた鳴滝塾。
聖医像遠まなざしに夏の雲
長崎の興善町に生まれた芭蕉の高弟、向井去来の句碑も日見峠に建っています。
去来塚剥落なぞるも春愁
被爆地としての長崎も忘れる事は出来ません。
花冷えの礫像にある被爆痕(浦上)
江戸時代の殉教に始まる切支丹との関係も興味深いものがあります。
異教徒吾も心にベール致命祭(西坂殉教地)(写真110-1038)
十字架山霞む裾まで家迫り(十字架山)
汗の子の魚臭ほのかに二番ミサ(深掘)
聖堂の椅子の背にある神の冷え(浦上)
母のベールより手を出し聖夜の子(クリスマス)
長崎は、他にまだまだ俳句の素材として、他県の人々を感動させるのに十分な場所や行事が沢山あります。みなさんも長崎を歩いて、新しいポエムを発見しませんか。
宮田カイ子さん
俳人。俳人協会会員。俳誌『天為』長崎支部長。
俳句歴30数年のキャリアを生かし4つの句会の主宰、時津の公民館講座の講師も務めておられる。
現在、お弟子さんの数は約50名。若い方が多いのも特徴だとか。
今回紹介くださった俳句も含め、長崎の情景を詠んだ俳句を盛り込んだ句集も出版しておられる。
次回は、宮田さんの俳句会の会員で、詩人でもある田中俊廣さんにご執筆いただきます。
|