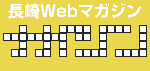|
 |
五月の節句近くになると、昔の長崎の家庭ではちまきを作り、食べていたものです。独特の風味がして、子供にとっては砂糖やきなこをたっぷりかけても苦手な食べ物だったかもしれません。大人になってあらためて食べてみて、その風味と味のとりこになったという人もいます。
長崎のちまきは「唐灰汁ちまき」ともいいます。唐灰汁は中国から伝わったもので、形は石灰のように白い固形物です。現在のちまきはこの唐灰汁を使ったものがほとんどですが、昔は単に灰汁だけを使ってちまきを作っていたそうです。
カステラ屋さんや和菓子屋さんなど、薪をたくさん使うところで一升瓶に入れて売られていました。なぜ灰汁を唐灰汁とわざわざ言っていたのか、それはよくわからないのですが、中国となじみの深い長崎独特の言い回しかもしれません。 |
 |
「唐灰汁ちまき」は、唐灰汁のうわ澄み液にひたした餅米を袋につめ蒸してつくります。食べるときに適当な大きさに糸で切っていきます。ちまきが柔らかくべたつくので、包丁で切るよりも糸で切る方がきれいに切れるのです。器用に糸で切る様を見ていると、長崎に唐人さんがいたころにタイムスリップしたような感じを受けます。 |
 |
 |
唐灰汁は長崎のちゃんぽん麺にも使われている、地元の人にはなじみの深いものですが、唐灰汁の製造業者が少なくなっているのが気になります。中国から伝わった、長崎ならではの「唐灰汁ちまき」、季節の味覚として大切に伝えていきたいものです。 |
|