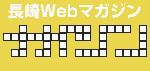|
 |
長崎名物といえば、ちゃんぽん、皿うどん。長崎人は、家でも店でも職場(出前)でも、冬の寒い日はもちろん、真夏にさえ汗を流しながら食す、とても馴染み深い食べ物です。
それでは、このちゃんぽん、皿うどんの味で一番肝心なものはさて何でしょう。 具材? スープ? これももちろん大切ですが、それは・・・なんといっても麺。長崎のちゃんぽん、皿うどん麺は唐灰汁(とうあく)が入った独特の麺なのです。
そもそも唐灰汁という言葉自体を知っている人が少なくってきました。昔は、端午の節句には各家庭でちまきを作っていました。この長崎特有のちまきに使うのも唐灰汁。長崎人は子どもの頃から唐灰汁が創り出す、独特の香りと味に親しんできたのです。 |
 |
カンスイとも呼ばれる唐灰汁は、でんぷんと混ぜると独特の匂いと粘りを出すため、中国料理の麺づくりに欠かせないものでした。これが上海から長崎に伝わったのは昭和初期。この唐灰汁と小麦粉とを配合したのが唐灰汁麺です。唐灰汁伝来から80年余り。今や唐灰汁麺を使わないちゃんぽん、皿うどんは長崎の味ではないという人もいるほど、長崎人にとって唐灰汁麺は、まさにちゃんぽん、皿うどんの要といってもいい存在となりました。 |
 |
 |
唐灰汁の利いたちゃんぽん麺は存在感のある個性が強いもの。甘味、旨味、独特の風味が、各店のスープやアンの個性と相まって口の中で大きく花開きます。また、長崎人は皿うどんの細麺のことを「パリパリ」といいます。たっぷりアンのかかった皿うどんに箸を入れると、パリッと音がするし、噛めば口の中でパリパリするからだと思います。このパリパリ麺にも普通の細麺を基準に、極細麺、そして細麺の中の太麺があり、この麺の太さが各店の特徴のひとつとなっています。 |
 |
胃を殺菌したり、油を中和させたりする作用がある唐灰汁は、実は薬品(炭酸ナトリウム、炭酸カリウム)。そのため製造するには許可が必要で、国内で長崎だけでのみ製造されています。それも製造者は長崎市内にわずか4名だけだとか・・・。つまり、全国各地でちゃんぽん、皿うどんが食べられるようになったとはいえ、唐灰汁麺を使用した「本場、長崎ちゃんぽん、皿うどん」が食べられるのは、ほぼ長崎市内だけなのです。
今度、長崎ちゃんぽん、皿うどんを食べるときには、ぜひ唐灰汁麺の持つ独特な味わいとコクを噛みしめながら、じっくり堪能してみてはいかがでしょう。 |
|