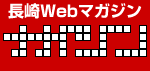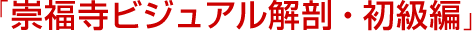2.護法堂(ごほうどう)〜大釜(おおがま)
●関帝の仇をとった韋駄天(いだてん)話●
第一峰門を背に奥へと進んで行こう。
右手にある土産物店で長崎限定発売の『長崎チャイナリカちゃん』を発見!
こんなレア物があるなんて知らなかったぁ! という長崎の人も多いのでは?
立石さん
「さて今度は護法堂前で、目線を下の方へ向けてみて下さい。
護法堂の建築的な面での特徴の一つがコレです」
護法堂の柱、足元に目線を落とす。
と、太鼓状にふくらんだ礎盤に彫刻が刻まれている。
そのモチーフは
立石さん
「ここにも中国で縁起がいいとされるものが刻まれているようです。
例えば鹿。中国では鹿は千年で蒼鹿となりそれから500年経つと白鹿に、さらに500年経ると玄鹿に化すと言われ、長寿の仙獣とされています。
また、日本の七福神にあたる中国の神様、福禄寿の「禄」と同音同声であるため、文字の上からも長寿の象徴、吉祥文様とされているようです」
鹿が縁起物なんて知らなかった〜。
だから奈良には鹿が多いとか?
立石さん
「この護法堂には面白い話が言い伝えられているんですよ。
関帝像前に菓子や食べ物を供えると、よくねずみに食べられるので、寺僧は供物を食べられるようでは霊験(神仏が示す不思議な利益)があるものかと笑っていたそうです。
ある日、即非和尚が関聖像に向かい、ねずみに食べられる罪を責めて右の頬を打つと頬の部分が剥げてしまいました。
で、翌朝見ると、韋駄天の剣にねずみが刺し抜かれており、まるで関聖の命令で韋駄天がねずみを退治したようだったそうです。
寺僧もこれには驚き、早速関聖帝像の右頬の修理をさせましたが、剥げた部分にいくら漆を塗ってもどうしてもうまく付かず、今もその跡が残っているというんです。」
あるある!
暗くて分かりづらいけど、関帝にしてみれば右の頬、向かって左の頬に白い傷跡が……。
続いて韋駄天へ目を移すと、何ごともなかったように穏やかな表情で立っている。
本来、本尊の釈迦如来を守るのが韋駄天の役割なのだとか。
現代でも足が速い人のことを韋駄天というが、この護法堂の中を駆け回りねずみを素早く退治するのはやはり韋駄天にしかできなかったかも。
 |
 |
|
護法堂横には国指定重要文化財の鐘鼓楼、そしてその前に巨大な釜が置かれている。
立石さん
「延宝年間末頃(1681年頃)不作のため米価が上がり、長崎でも飢餓に迫られる状況に陥りました。
崇福寺でも施粥(せじゅく)をはじめましたが日々1000人を超えるようになったそうです。
更に飢饉は続き普通の鍋では到底間に合わないようになったため、鍛冶屋町の鋳物師に注文してこの大釜を造らせたそうです。
一度に米630キロ(4200合)を炊き、飢饉に苦しむ3000人に施粥したと伝えられています。
多い時は5550人だったというから驚きですよね」
多くの人を飢えから救ったこのでっかい大釜は、崇福寺の功労者なのだ。
|
 |
 |
コウモリをトレードマークにしている某カステラの老舗は、当時米も商っていたため、この施粥に際し32俵もの米を寄進されたのだとか。
(1俵は約400合なので32俵というと約12800合でかなりの量)。
屋号の「福」は中国の福州からきているとか。
3.大雄宝殿(だいゆうほうでん)
●世にも珍しい内臓を持つ仏像様?●
立石さん
「この大雄宝殿ですが、初めは単層、つまり1階建てだったんです。
天和元年(1681)頃、2階建てに重層化されました。
ここで面白いのが下の層(1階)は黄檗様で上の層(2階)は和様ということ。
日中合作の建造物でありながら、一見何の違和感もなく調和しているところですね」
説明されるまで気づきませ〜ん。
双眼鏡でズーム。
良く見ると1階屋根軒丸瓦の瓦頭には崇福寺の「崇」、2階屋根瓦頭には「福」の文字がある。
2つ合わせて崇福寺というわけだ。
 |
 |
|
さて、大雄とは、釈迦如来のことを指し、この中に本尊である釈迦如来三尊坐像が安置されているので大雄宝殿と言うらしい。
立石さん
「この仏像には内臓があるんですよ」
えっ?内臓って?胃とか腸とか心臓とか?
仏像に内臓、ってことは生き仏?
ちょっと意味が違うか。
|
 |
|