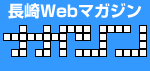 |
|
 |
||||
文・宮川密義 |
||||
|
||||
|
江戸、大坂で大流行 なかでも「九連環(きゅうれんかん)」は明清楽の代表曲として有名になりました。 「九連環」は“九つの環でできた知恵の輪”のことで、次のような中国語の歌詞があります。 |
||||
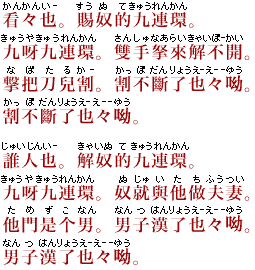 |
||||
| 意味は 「見ておくれ、わたしがもらった九連環。九とは九つの連なった環のことよ。両手で解こうとしても解けません。刀で切ろうとしても切れません。ええ、なんとしょう」 「どなたかいませんか、解いてくれる人。その人がいたら夫婦になってもいい。その人はきっと好い男」という意味。 「九連環」は、次の替え歌「かんかんのう」を生みました。 |
||||
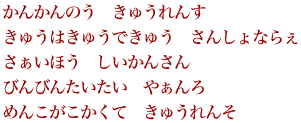 |
||||
|
||||
|
明治から昭和まで替え歌続出 「かんかんのう」は明治(1868〜1912)になって、さらに「ホーカイ節」(春風に 庭にほころぶ梅の花、鶯(うぐいす)とまれやこの枝に ホーカイ、そちがさえずりゃ 梅がモノ言う心地する ホケキョ ホケキョウ…)や「さのさ節」「むらさき節」「くれ節」「鴨緑江節」「満州節」「とっちりちん」などと形を変えながら、はやり続けます。 明治には“梅ヶ枝の手水鉢(ちょうずばち) 叩いてお金が出るならば、 若しもお金が出た時は その時ゃ 身受けをそうれ頼む…”の「梅ケ枝節(うめがえぶし)」が生まれ、昭和12年(1937)には“もしも月給が上がったら、私(あたし)はパラソル買いたいわ、僕は帽子と洋服だ…”の「もしも月給が上ったら」(林伊佐緒、新橋みどり・歌)になります。 昭和29年に作られ、宴会での余興に歌い踊られ、お座敷ゲームでも楽しまれた“野球するなら こうゆう具合にしやしゃんせ…”の「野球拳」もこの流れを酌むものです。 このように、長崎発の明清楽「九連環」は日本流行歌謡の源流の一つとして、最近まで生き続けているわけです。 |
||||
|
|
||||
| 【もどる】 |

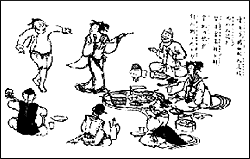 長崎名勝図絵に描かれた
長崎名勝図絵に描かれた