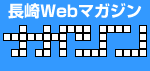 |
|
 文・宮川密義 |
|
|
| 日蘭交流400周年の平成12年(2000年)から10年過ぎ、2010年は410年目に当たります。オランダの文化は中国文化とともに、長崎市民の生活に浸透していますし、長崎の歌の大部分に“オランダ”が登場しています。題名に「和蘭陀」「阿蘭陀」「オランダ」「おらんだ」を付けた歌だけで40曲、歌詞に取り入れた曲も含めるとかなりの数にのぼります。 歌の中のオランダについては、バックナンバー32「“長崎のオランダ”を歌う(上)」と33「“長崎のオランダ”を歌う(下)」で取り上げましたが、今回から続編として、それ以外の歌の中から数曲、年代順に紹介することにしました。 |
||||||
| 1.「阿蘭陀船の唄」 |
||||||
| (昭和11年=1936、山田としを・作詞、南 良介・作曲、東 光子・歌) | ||||||
 |
||||||
|
||||||
2.「おらんだ草紙」 |
||||||
| (昭和16年=1941、野村俊夫・作詞、古関裕而・作曲、霧島 昇・歌 ) | ||||||
 |
||||||
|
||||||
3.「長崎のオランダ娘」 |
||||||
| (昭和26年=1951、吉川静夫・作詞、吉田 正・作曲、平野愛子・歌) | ||||||
 |
||||||
|
||||||
4.「別れのオランダ船」 |
||||||
| (昭和27年=1952、阪口 淳(さかぐち・じゅん)・作詞、服部良一・作曲、服部富子・歌) | ||||||
 |
||||||
|
||||||
5.「オランダ夜船」 |
||||||
| (昭和28年=1593、吉川静夫・作詞、吉田 正・作曲、渡辺はま子・歌) | ||||||
 |
||||||
|
||||||
6.「雨のオランダ屋敷」 |
||||
| (昭和31年=1956、牧 喜代司(まき・きよし)・作詞、水時富士夫(みずどき・ふじお)・作曲、西村正美(にしむら・まさみ)・歌 ) | ||||
 |
||||
|
【もどる】 |




