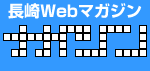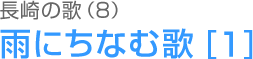|
長崎の雨を歌ったものは、タイトルの上では45曲程度ですが、ほかの歌にも歌詞の中には随所に雨が出ています。
歌われる雨は“こぬか雨”や“霧雨”のようなロマンチックなムードをたたえています。
しかし、実際に降る雨はそれほど多くはないようで、降り始めると集中雨的に降ることが多いといわれます。
昭和57年(1982)の長崎豪雨では1時間当たり 187ミリ(長与)にも及び、坂の町の地形も災いして多くの犠牲者を出しました。
歌の中で降る雨はどんな雨でしょうか。
まずはそのものズバリのタイトルの歌から…。
|
1.「長崎の雨はどんな雨」
(昭和50年、岡田冨美子・作詞、三木たかし・作曲、岡崎 徹・歌)
|

|
|
|
2.端唄「春雨」(弘3年=1845)
|
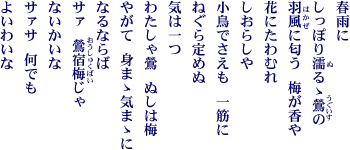
|
|
しっとりとした春雨は、梅の香りやウグイスを呼び、日本的な情緒をかもし出してくれます。
全国的に知られる端唄「春雨」は長崎・丸山生まれで、今でも名曲として歌い継がれています。
詳しくはバックナンバー「(3)春雨、浜節、長崎甚句」をご覧下さい。
|
3.「長崎の雨」(昭和26年、丘 灯至夫・作詞、古関裕而・作曲、藤山一郎・歌)
|
|
|
|
|
4.「雨のオランダ坂」(昭和22年、菊田一夫・作詞、古関裕而・作曲、渡辺はま子・歌)
|
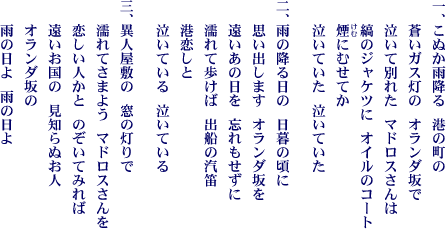
|
|
|
5.「雨の長崎」(昭和27年、阪口 淳・作詞、吉田 正・作曲、渡辺はま子・歌)
|
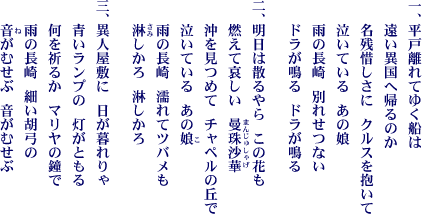
|
|
前記「長崎の雨」に似た時代の長崎が舞台です。
異国に帰る恋人との別れの悲しさを雨にのせて描写しています。
歌う渡辺はま子さんは中国での抑留生活を終えて帰国後、第1回吹き込みが前項の「雨のオランダ坂」でした。
「雨のオランダ坂」以後はしばらくヒットが出なかったようですが、3年後、「シスコ桑港のチャイナタウン」で再びスターの座に帰り咲き、昭和27年(1952)に、この「雨の長崎」となりました。
|