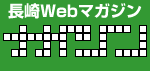|
TEL095(847)9245 上銭座町3-1
開館/ 9:00〜17:00(入館は16:30まで)
入館料/ 無料
休館/ 月曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)
駐車場/ 15台
|
●JR長崎駅からのアクセス
路面電車/長崎駅前から赤迫行きに乗車し、茂里町電停で下車、徒歩10分。
バス/長崎駅前バス停から長崎バス医大経由下大橋行きに乗車し、目覚町で下車、徒歩7分。または立山行きに乗車し、あじさい荘下車、徒歩3分。
長崎駅前バス停から県営バス目覚経由立山行きに乗車し、あじさい荘下車、徒歩3分。
車/長崎駅前から約8分
|
他の地域には見られない
独特の文化を持つ長崎 |
|
海外文化の影響を強く受けた長崎の街。この影響は市民生活にまでとけ込み、風俗、習慣、祭りなどの年中行事と、現代の長崎にもしっかり息づいている。そのため、他の地域の民俗資料館には類をみない、異国情緒あふれる展示内容が魅力。長崎の昔の暮らしぶりを体感できる長崎市歴史民俗資料館へ……探検隊いざ潜入!
|
|
学芸員が教えてくれる
歴史を語る展示品の魅力 |
|
|
おすすめチェックポイントベスト3
1. 南蛮屏風に描かれた犬?
2.千年前の長崎俵物?
 |
 |
出島が世界に開かれた唯一の窓口だった鎖国時代、出島から全国へ様々なものが流通した……というイメージが一般的。しかし、それより遥か昔、今から約千年も昔から長崎で製造された石鍋が全国へ流通していた! 当時、船で運搬していたが、その船が遭難。海の岩礁などに着生しているフジツボが付着した鍋が近年、漁師によって引き上げられ発覚したのだ。千年前というと平安時代後期。う〜む、ビックリ!(1階)
|

『滑石製石鍋』 |
3.見て触って!体験しながら“昔”を学ぶ
|
|
長崎市歴史民俗資料館では、『企画展』も年間10回程度、また各方面の専門家を招いた『歴史文化講演会』が数多く開かれている。そのため、決して1度の訪問で満足してはならない! 訪ねる度に違う発見ができるのが魅力なのだ。あらかじめ電話で企画展の情報などを入手して、長崎の文化遺産の宝庫・
長崎市歴史民俗資料館をぜひ訪れてみよう。
|