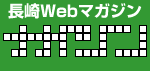 |
|
 |
|
長崎市立博物館 館長 原田博二 |
| 長崎・諏訪神社の秋の大祭くんちにちなんで、祭礼行列図や傘鉾の垂、奉納踊の衣装、絵はがきなど、くんちに関する資料約100点を展示いたします。 なお、今回、初めて国立民俗博物館所蔵の「長崎諏訪祭礼図屏風」(6曲1隻)が14日(日)まで展示されますとともに、 同歴史民俗博物館で制作された「風流のまつり長崎くんち」のビデオを期間中上映いたします。 |
||||
企画展示 風流のまつり「くんち資料展」 会期 平成13年9月30日(日)〜10月21日(日) 開館時間 9時〜17時月曜日・休館 会場 長崎市立博物館企画展示室 長崎市平野町7番8号平和会館内 TEL(845)8188 FAX(845)8119 入館料 大人100円 小中生50円 |
||||
| 諏訪神社大祭式行列図 | ||||
 |
||||
江戸時代のくんちは、9月7日に渡御(おくだり)、9日に還御(おのぼり)(寛政5年以降は9日に渡御・11日に還御と変更)が行われました。本図は7日の渡御を描いたものですが、当時の渡御のコースは馬町から桜町までは現在と同じですが、興善町から新町に入り、本博多町、島原町(以上、現万才町)を経て、御旅所に向かいました。 |
||||
| 長崎諏訪祭礼図屏風(国立歴史民俗博物館蔵) | ||||
 |
||||
長崎の諏訪神社とその祭礼(くんち)を描いた屏風ですが、今回初めてこれが長崎の諏訪神社と確認されました。本屏風は左隻の部分で、画面の一番左上が諏訪神社、中央が一の鳥居(現二の鳥居)、一の鳥居の左には大悲庵、能仁寺(以上、廃寺)、そして一番右に少し見えるのが松の森天満宮の鳥居です。一の鳥居からこの松の森天満宮の鳥居に至る流鏑馬馬場では、9日の還御直後に行われる流鏑馬が、諏訪神社の回廊内の能舞台では12日に行われる神事能がそれぞれ描かれています。 |
||||
| 刺繍入獅子唐子衣装・川船飾船頭衣装 | ||||
 |
||||
唐子踊や川船の飾船頭の衣装で長崎刺繍が施されています。長崎刺繍の技法は中国から伝えられたものですが、刺繍の部分が肉太く、量感があるのがその特徴です。 |
||||
| 本籠町傘鉾垂 | ||||
 |
||||
“金の中村”と称された長崎の豪商中村盛右衛門が、文化年間(1804〜1818)に制作させたもので、猩々緋(舶来の深紅色の毛織物)に飛龍が刺繍され、長崎刺繍の代表的な資料です。なお、この垂れは、現在、天地が短くなっていますが、これは、この垂れが後に中村家の菩提寺・禅林寺(長崎市寺町)の本堂内陣の帳として使用されたためでした。 |
||||
| くんちとは | ||||
 |
||||
最初にくんちが行われたのは、寛永11年(1634)のことといわれています。 このくんちは、陰暦の9月9日に行われましたので、“くんち(9日)”と呼ばれました。 この陰暦の9月9日というのは、五節句の一つで重陽とか菊の節句とか呼ばれました。重陽というのは、9は陽数といって縁起の良い数字で、しかも9月9日と9が2つ重なることから重陽と呼ばれました。 また、菊の節句というのは、この9月9日は菊の日と呼ばれ、この日の菊の下葉に宿る露や、菊の花を浸したお酒を飲むと長生きをするといわれたからでした。 このように9月9日というのは、とても縁起の良い日だったのです。 |
||||
| 諏訪神社とは | ||||
 |
||||
諏訪・森崎・住吉の三社は、最初は別々に祭られていましたが、寛永2年(1625)に唐津から来た青木賢清が三社を円山(現在の松ノ森神社の地)に合祀したと伝えられています。 慶安元年(1648)に現在地に移転しましたが、寛文9年(1669)に朱印地、さらには享保8年(1723)に正一位に叙せられるなど、江戸時代は幕府の手厚い保護のもとにありました。 しかし、安政4年(1857)の火災で社殿をことごとく焼失、明治元年に復興しました。同5年に県社、さらに大正4年に国幣中社に列せられました。 |
||||
| 傘鉾とは(写真は金屋町の傘鉾) | ||||
 |
||||
奉納踊を先導するのが傘鉾です。 長崎の傘鉾は、元来、祭礼に用いる鉾の非常に発達したもので、他の地方には見ることのできない独特のものです。 傘鉾の上部の飾物は、“だし”と呼ばれ、丸い笠のような台の上に取り付けられていますが、その輪を縁、または、輪といい、この輪の部分から下げられる織物のたれを、幕、“さがり”、“たれ”と呼びました。 この笠には、中央部分に穴があり、棒が通してあって、傘鉾持ちは、これを持つのですが、この棒には一文銭が3000枚ばかりも巻きつけてあり、上と下との重量の平均をとるようにしてありました。 輪には、注連と黒ビロードの二種類があり、黒ビロードには金糸で町名が縫い付けてあるのが普通です。もともと傘鉾の“だし”は、単に町名を記す標のようなもので、非常に簡単なものでしたが、次第に大きく複雑なものとなり、さらには、豪華なものとなっていきました。 また、“だし”が発達していない頃は、“たれ”を重要視し、唐織金襴が用いられました。 “たれ”も、最初は短いものでしたが、“だし”の発達とともに、“たれ”も次第に今日見るように長いものとなりました。 |
||||
| 奉納踊とは | ||||
奉納踊には、本踊、曳物、担物、通物などがありますが、川船や龍船に代表される曳物、コッコデーショに代表される担物などは、今日では、龍踊と同様、くんちの花形となっています。 ところで、今日余り奉納されなくなったものが通物です。 通物というのは、いろいろな行列の模様を再現したもので、本石灰町のアニオーさんの行列や、銀屋町の鷹野狩、八幡町の山伏の行列、江戸町の阿蘭陀兵隊さんの行列、鞠屋町のお茶献上行列などは代表的なものでした。 特に、本石灰町のアニオーさんの行列は、御朱印貿易家荒木宗太郎の許に輿入れする安南国の王女アニオーさんの行列の模様を再現したもので、通物の内でも随一と称されました。 ところで、このアニオーさんの行列の模様が、非常に華美で仰々しかったので、長崎では、近年まで華美で仰々しいことを、“アニオーさんの行列のごたる”といったということです。 |
||||
|
||||
| 【もどる】 |