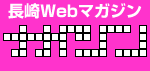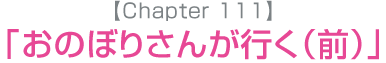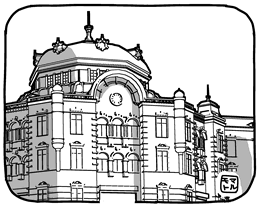(東京駅にて)
あいやー、また人の多かこて!
空港からここに来るまでも
たいがいやったばってん、東京駅の人の多かこて。
もうまるで、お旅所んごたる。
こげん人の多かとは、きっと
汽車の着いたばっかいやっけんばい。
どれ、人ん少のうなって歩きやすうなるまで
改札口ん横に立って、待っとりましょうだい。
《訳》
ああ、また人が多いこと!
空港からここに来るまでも
ものすごかったけれども、東京駅に人が多いこと。
もうまるで、お旅所みたいだわ。
こんなに人が多いのは、きっと
電車が着いたばっかりだからだわ。
そうだわ、人が少なくなって歩きやすくなるまで
改札口の横に立って、待っていましょう。
(そして10分後)
へんなかね……いっちょん人の減らんばい。
長崎やったら、汽車ん着いた時間は混むばってん
あとはゆたーってしとるとに……。
(ハッと気付いて)あいやーそうやった!
ここは東京やもん、列車の数もたいがいばい!
改札口ん人の減るはずなかばい。
いやー恥ずかしかー!(そそくさと去る)
《訳》
おかしいわ……まったく人が減らないわ。
長崎だったら、電車が着いた時間は混むけれども
あとはのんびりしてるのに……。
(ハッと気付いて)ああーそうだった!
ここは東京だもの、列車の数もものすごく多いんだわ!
改札口の人が減るはずないんだわ。
いやだ恥ずかしい!(そそくさと去る)
(とある料理店に入り)
恥ずかしかったけん、お腹んすいたばい。
えーと(メニューを見て)何ば食べようかな……
うわあ高さー! 何でこがん高かとやろ!
長崎で700円で食べらるっもんの、1000円すっばい。
ばってん入ったけんしょんなか。注文せんばよね。
(注文した料理が来る)
どれひとくち……うわ、予想しとったとと違う。
なんかからか。長崎ん遠かばい……。
《訳》
恥ずかしかったから、お腹がすいたわ。
えーと(メニューを見て)何を食べようかな……
うわあ高いー! 何でんなに高いんだろう!
長崎で700円で食べられるものが、1000円になってるわ。
でも入ったからしょうがない。注文しなくちゃね。
(注文した料理が来る)
どれひとくち……うわ、予想していたのと違う。
なんだかしょっぱい。長崎が遠いわ……。
<ワンポイント>
【たいがい】
「ものすごく(ひどい)」「とても(大きい)」など
形容詞の程度が大きいときに、形容詞抜きで使われる。
例/「あん人は、たいがいやもん」
(「あの人は、ものすごく大変だもの」)
【お旅所んごたる】
「お旅所」は、長崎諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」で
御神体がとどまる場所。
祭りの3日間、大波止に設けられるが
その期間中の大波止近辺は、未曾有の大混雑となる。
おかげで、長崎の人間は、ものすごく人の多い状況を
「お旅所んごたる」と言いあらわすことが多い。
【汽車】
JRの終着駅である長崎は
公共交通機関というと、バスか路面電車のことをいう。
ほとんどの長崎の人間は、遠出をするときにしか列車に乗らない。
また「電車」といえば「路面電車」を意味することから
JRの列車のことは「汽車」と表現する人がいる。
とくに、国鉄時代を知るような年配の人に多い。
(若い人は「JR」と言っている)
【ゆた〜って】
ゆっくりと。のんびりと。
例/「動かんちゃよかけん、ゆた〜ってしとかんね」
(「動かなくていいから、のんびりしておきなさい」)
【からか】
しょっぱい。塩からい。
「スパイシー」「ホット」の意味より
しょっぱいの意味合いで使う場合のほうが多い。
例/「こんカレー汁、ぼっくいからか」
(「このカレー汁、ものすごくしょっぱい」)
【長崎ん遠か】
江戸時代、他の土地に比べ、砂糖が簡単に手に入っていた長崎では
料理のいちばん大事な味付けとして、砂糖が使われていた。
そのため一部の地域では、料理に甘さが足りないときには
「長崎が遠い」というふうに表現するそうだ。
ふだん使いの味噌や醤油も、甘味が強く
自分たちがそんなに甘いものを食べているという自覚がないため
他の土地(特に東日本)に行って、愕然とする。
|