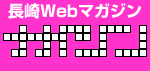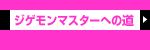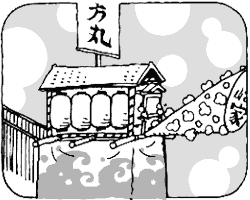|
(責任者用の青いタスキをつけた夫のもとに
赤ん坊を抱えて、妻がやってくる)
妻 あなた、こもん準備の出来たばい。
夫 おう、こっちも見れ! 立派か精霊船やろもん。
妻 おうちと従兄さんと、意地んなって作業しよらしたとの
どげんとの出来(でく)っとやろって思いよったら、すごかねぇ。
(赤ん坊にむかって)ほーらお船ばい、きれかやろう。
夫 …けっきょくこん子は、ばあちゃんとの思い出ば
いっちょも、作られんやったけん…
妻 こん子?
夫 せめて「な〜んかこまんか頃に、ピカピカしたふっとか船んあって
ぼっくい人の来て、にぎやかかったなあ」…って
そがん思い出でんよかけんさ
おい、こん子に作ってやりたかったと。
妻 あなた…。
《訳》
妻 あなた、こもの準備が出来たわよ。
夫 おう、こっちも見ろよ! 立派な精霊船だろう。
妻 あなたと従兄さんと、意地になって作業していたけれども
どういうのが出来るのかしらって思っていたら、すごいわねぇ。
(赤ん坊にむかって)ほーらお船よ、きれいでしょう。
夫 …けっきょくこの子は、ばあちゃんとの思い出を
ひとつも、作れなかったからな…
妻 この子?
夫 せめて「な〜んか小さい頃に、ピカピカした大きい船があって
たくさん人が来て、にぎやかだったなあ」…って
そんな思い出でもいいからさ
おれ、この子に作ってやりたかったんだ。
妻 あなた…。
(火気管理者の赤いタスキをかけた従兄がやって来る。
酒もほどよく入り、ごきげんそう)
従兄 おい、そろそろ出発したがよかっちゃーなかか?
遅うなったら、県庁坂んにきで混むばい。
夫 そうばいね。出発すうか。
あ、そうや! 東京からきたおじさんはどげんしとる?
従兄 こいから何のはじまるとかって、目ばしろくろさせとる。
「忘れんごと耳栓ばして、いっしょに船ば押して下さい」
ちゅうとったけん、ま、大丈夫やろう。
ばってん、おいたちが夜火矢ば飛ばすとこば見たら
おったまがるやろうね。そいに、あん爆竹も。
《訳》
従兄 おい、そろそろ出発した方がいいんじゃないか?
遅くなったら、県庁坂のあたりで混むぞ。
夫 そうだね。出発しようか。
あ、そうだ! 東京からきたおじさんはどうしてる?
従兄 これから何がはじまるんだって、目をしろくろさせてる。
「忘れないように耳栓をして、いっしょに船を押して下さい」
と言っておいたから、ま、大丈夫だろう。
だけど、おれたちがロケット花火を飛ばすとこを見たら
たいそう驚くだろうね。それに、あの爆竹も。
(ゾロゾロと短パンに腹掛け、ハッピ姿の男衆が集まる。
女性や子どもたちも、思い思いの位置につく)
妻 行ってらっしゃい。わたしはこん子とお留守番ばしとります。
(赤ん坊にむかい)ばあちゃんにバイバイばしよう。バイバ〜イ。
夫 …おぼえとってくるっかなあ、こいつ。今夜の事ば。
妻 心配せんちゃよかさ、ちゃんとおぼえとってくるっさ。
あれ…なんかいま、写真の中んお義母さんの、笑ったごたる気のした。
夫 お、こいつも笑うたぞ。
《訳》
妻 行ってらっしゃい。わたしはこの子とお留守番をしています。
(赤ん坊にむかい)ばあちゃんにバイバイをしよう。バイバ〜イ。
夫 …おぼえててくれるかなあ、こいつ。今夜の事を。
妻 心配しなくていいわよ、ちゃんとおぼえててくれるわよ。
あれ…なんかいま、写真の中のお義母さんが、笑ったような気がした。
夫 お、こいつも笑ったぞ。
「パパパン!パンパンパン!」はげしく爆竹が鳴る。
「チャンコンチャンコン」と鐘の音。
「ドーイドーイ」のかけ声とともに、静かに船はすすみはじめる。
<ワンポイント>
【精霊船】
「船」といっても現在は、実際に海に流すわけではない。
大きな「みよし」に家名を入れ、盆提灯を左右にいくつか下げて
思い思いにかざりつける、というのが基本のかたちである。
大きさは、数人で持てるものから、何連にも連なったものまでさまざま。
【こも】
かやなどで、ご飯や果物などのおそなえものを包み、ワラ納豆のような形にしたもの。
精霊船に乗せ、一緒に流す。
【県庁坂】
県庁坂のあたりが、精霊流しのいわゆる「メインステージ」。
ここをカッコよく通りたいがために、皆さまざまな苦労をする。
とくに時間の調節は重要。早すぎるとまだ客がいなかったり
遅すぎると、途中で3時間ぐらい待つハメになったり、そりゃもう大変。
【夜火矢(やびや)】
ロケット花火のこと。これをじかに手に持ったり
竹ひごの部分に、もう1本の矢をひっかけたりして上げるという
とてもキケンなワザが、いわゆる長崎流。
(よいこのみなさんは真似をしないでくださいね)
【爆竹】
爆竹を鳴らして魔をはらう、という中国伝来のこの習慣は
けっこう長崎の土地に根付いている。
爆竹が、耳元でパンパン鳴っても「キャー」なんて悲鳴をあげるのは野暮。
なるべく平気な顔をしていなければならない。
子どもなどはこれが鳴らせないと、一人前とは認められないのだ。
【チャンコンチャンコン、ドーイドーイ】
精霊流しが行くときの、鐘の音とかけ声を表現したことば。
「ドーイドーイ」は「南無阿弥陀仏」がちぢまって
こう言われるようになったらしい。
次回へつづく… |