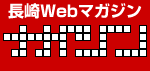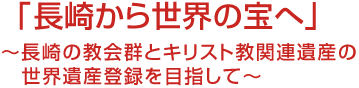|
 |
| |
| 今、長崎県はふたつの項目の世界遺産登録に向けて歩みを進めている。対象のひとつは、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」。そしてもうひとつが「九州・山口の近代化産業遺産群」の一翼である小菅修船場跡、長崎造船所関連施設、高島炭鉱、端島炭坑、旧グラバー住宅だ。いずれも、長崎という町が形成されてきた歴史の中で、常に支柱となってきた「長崎の宝」と呼べる存在--。 |

小菅修船場跡 |

端島炭坑(軍艦島)
|

旧グラバー住宅 |
世界遺産登録への動きは、長崎の成り立ちと歩みを世界にアピールする格好の機会!というわけで、今回のナガジン!では、ひと足先に動きはじめた「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の全貌に迫るべく、長崎市にとどまらず、県下における「キリスト教の歩み」をおさらいしてみたい。 |
なお、連動して1年間、全12回の連載コラム「長崎の教会群 その源流と輝き―長崎の教会群とキリスト教関連遺産を世界遺産へ―」をスタート。毎回テーマを掲げ、より掘り下げた情報を展開することにした。こちらも是非、チェックしてほしい!
※長崎の教会群 その源流と輝き―長崎の教会群とキリスト教関連遺産を世界遺産へ―参照 |
長崎県のカトリック信者数 |
| さて、現在、日本におけるカトリック信者数は、448,440人(「カトリック中央協議会」HP 2010年データより)。そのうち、長崎教区(全国で16に分類)のキリスト教信者数は63,081人。これは、96,146人の東京教区に継ぎ全国第二位の数で、対人口比率でいうと、東京教区が0.51%に対し、長崎教区は4.35%。なるほど!友人知人にカトリック信者が多いのも納得の数字だ。 |
長崎県(教区)の教会堂数 |
また、改めて数字にして驚くのは教会堂の数。長崎教区は、全国でも最多の133の教会堂が存在。なかでも特徴的なのは、小教区数の教会堂が71(そのほか準小教区1、集会所1)に対し、離島や農村小規模の巡回教会が60もあることだ。
今年はキリスト教が平戸に伝来してから462年。その間、繁栄、禁教、潜伏、復活という長く厳しい時代をくぐり抜け、「新たなキリスト教信仰」の形へと展開を遂げた姿を示し続けているのが、現在も長崎県下、各地に点在する教会堂なのだ。それでは時をさかのぼり、9つのキーワードをもとに「長崎のキリスト教史」に潜む数多くの物語を紐解いてみることにしよう。 |
| |
| |
伝来にはじまる
布教と繁栄の物語。 |
keyword.1……「イエズス会」
布教したのはザビエルなれど
町の創造者は神父トーレスなり。 |

平戸港
写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」 |
日本にキリスト教を布教したことで知られる聖フランシスコ・ザビエルは1534年に創立したカトリック教会男子修道会・イエズス会の創始者の一人。彼が平戸に下り立ったのは1550年(天文19)。彼が45歳のとき。40歳のコスメ・デ・トーレス、24歳のファン・フェルナンデスを伴ってのことだった。この年は、ポルトガルの貿易船が平戸港にはじめて入港し貿易を行った年だった。当時の平戸領主・松浦隆信(まつらたかのぶ)は、実のところポルトガル貿易で上がる利益は歓迎していたが、ポルトガル人やキリスト教は歓迎していなかった。が、貿易と分離することができないキリスト教の布教も渋々認めることに……。 |
この時ザビエル一行は“木村”という武士の屋敷に宿泊。ザビエルは平戸には長く滞在しなかったが、約ひと月の間に木村とその家族に洗礼を授けた。実質、これが長崎県における最初の布教であり、その後、わずかの間に受洗者の数は100人に達したという。
その後ザビエルは、都での布教計画のためフェルナンデスと数名の信徒を伴い旅立つ。平戸地方の布教活動は、パードレ(宣教師)コスメ・デ・トーレスに一任された。木村の家が平戸教会を置き、トーレスは最初の主任司祭となる。
信者の数が増えてくると、同じ港町の他の所に住居が移されたが、まだ教会と呼べる建物はなかった。 |

平戸 聖フランシスコ・ザビエル碑
写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」 |
布教が盛んになると、宣教師と仏僧との宗教的な争いなど、暗雲が立ち込めはじめ--永禄4年(1561)、言語不通が原因でポルトガル人と日本人の間に争いが勃発。ポルトガル船長をはじめ14名の死者を出した「宮の前事件」が起こる。そして、この事件をきっかけに平戸とポルトガル人との関係が冷え込んでいった。
するとトーレスは、平戸に変わる次なる港を探すことに……。 |
| |
|
keyword.2……「大村純忠」
次に開かれた港は
大村氏の領地・横瀬浦。 |

横瀬浦公園展望台からの眺望
写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」 |
翌年はじめ、当時5つの村を統治していた大村の大名大村純忠はトーレスに自分の領内でキリスト教を説くためにイルマン(修道士)の派遣を求める。それは、ひとつの港を教会に与えると同時に、その港をポルトガル貿易の自由港とするという提案だった。そして、トーレスが部下であるイルマンルイス・デ・アルメイダを派遣し次の候補地に選んだ場所こそ、純忠が申し出た横瀬浦の港だった。
この時29歳だった純忠は、肥前国の戦国大名(島原半島南目)の次男であり、天文7年(1538)に大村純前の養嗣子となり家督を継いだ人物だ。
横瀬浦開港にあたり、トーレスと純忠との間で4つの約束が交わされた。
1. キリスト教を広めることを認めること。
2. 教会を建てることを認めること。
3. 港の半分の土地をゆずること。
4. 商人に対して10年間無税にすること。
同年7月、純忠とトーレス間の交渉成立。翌年1563年6月には、純忠は横瀬浦の地で受洗し、日本初のキリシタン大名となった。 |
今も横瀬港のシンボルとなっている横瀬港の入り口に浮かぶ八ノ子島の十字架。開港した当時も、そこには大きな十字架が立てられ、入港するポルトガル船の目印となっていた(現在の十字架は1962年、南蛮船来航400周年記念に再建されたもの)。 |

八ノ子島(西海町)
写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」 |
しかし、開港後、大阪、堺、豊後などから押し寄せる貿易商人らがつめかけ、活気に満ちた横瀬浦の輝かしい時は、わずか1年4ヶ月で終焉を迎える--永禄6年(1563)8月、純忠に対する反乱が起き、11月下旬、横瀬浦は焼き討ちに遭い宣教師達はこの港を放棄したのだ。
このときすでに肥前の戦国大名有馬義貞(純忠の実兄)所領の口之津も南蛮貿易港として開港。アルメイダによって布教がなされていた。 |

南蛮船来航の地(口之津)
写真提供:長崎県観光連盟「旅ネット」 |
また、横瀬浦からいったん平戸に戻った宣教師達も、大村領での貿易を望み、1965年から福田港(現長崎市)に来航。しかし、外海に面し条件の悪い福田港より適した港が求められ、新たな港として選ばれたのが、深い入江の穏やかな長崎港だった。 |
| |
keyword.3……「長崎の町建て」
荒れ果てた寒村は、
開港と共に小ローマに変身。 |

長崎港 |
元亀2年(1571)、純忠の娘婿、長崎甚左衛門純景(すみがげ/彼も純忠に倣って受洗)の領地だった長崎の港がポルトガル貿易港として開かれ、港に突き出した岬(現在の県庁地)辺りを中心に6つの町が造成され貿易の拠点となった。このとき、各地から移り住んだ多くのキリシタンがこの町を発展させていくことに--。
しかし、長崎におけるキリスト教布教活動は、すでに永禄10年(1567)、トーレスの命を受けたアルメイダによってはじめられていた。布教の2年後には早くも長崎最初の教会堂トードス・オス・サントス教会(夫婦川町・現春徳寺)が建てられている。そして、元亀元年(1570)、ポルトガル貿易港として開港されると、さらに市中には多くの教会や関連施設が建造されていった。
※2002.2月 ナガジン!特集「シーボルトも歩いた道」参照
さらに天正8年(1580)、長崎6ヶ町と茂木をイエズス会に寄進。町全体がイエズス会領になると日本におけるキリスト教の中心地となっていった。また、天正12年(1584)には浦上村もイエズス会に寄進され、浦上村一帯がキリシタンの村となる。 |
| |