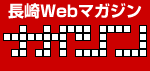 |
|
| ●大浦屋は時代と共に衰退、そして欺き |
|
| お茶の大産地静岡を控えた横浜港からの輸出が急速に伸びていった1860年代が終わりに近づくにつれ、お慶の茶の輸出は徐々に衰退の兆しを見せはじめる。この頃からお慶も新しい商取引を模索しはじめていたようだが、そんな折、熊本藩士・遠山一也から煙草の取引と偽られ、保証人になり裁判沙汰へと巻き込まれ、お慶はただ連判したという理由によって千五百両近い賠償金支払いを命じられる。これがいわゆる遠山事件、お慶43歳のときだった。こうして遠山事件をきっかけに、大浦家は没落を余儀なくされた。 お慶はこの取り調べに際し、長崎商人として、 また、一人の人間として義を持って戦ったといわれているが、 騙した側が士族や役所関係者だったため結果的に不当な責任を負わされた。しかも、この事件にはお慶の製茶貿易商としての道を切り開く際に力を貸した阿蘭陀通詞・品川藤十郎が関与していた事実が後の研究によって明るみに出てきている。 その後、大浦屋は没落の道をたどり、事業に失敗。長崎の豪邸の一つに数えられていた旧家は人手に渡ることになる。 このように晩年は不遇なお慶だったが、明治17年(1884)、明治政府はお慶に対し、茶輸出を率先して行った功績を認め、功労賞と金二十円を贈っている。すでに借金を払い終えたお慶にとって、この褒賞はせめてもの慰めとなったに違いない。がしかし、そのときお慶は危篤状態にあったのだという。 |
|
 |
 |
| 高平町の高台にある大浦家墓所。 昔は高野平(こうやびら)とよんだという。 |
|
●伊藤痴遊がつくりあげたお慶の虚像 |
|
大浦慶が長崎の女傑として、今もその名が語り継がれている理由として、お慶が大隈重信や坂本龍馬など幕末の志士達を金銭的に援助していて、大浦家には幕吏の追跡にあった志士達の隠れ家があったとか、お慶21歳のとき、市場調査のため茶箱に隠れてインドに密航し、数年を過ごし帰ってきたとか、はたまた結婚はしたが、気に入らなかったため、一晩で見切りをつけお慶の方から離縁をいい渡したとか、お慶について、まことしやかにいい伝えられている様々な伝説がある。 しかし、これらのいい伝えには、歴史的根拠がなく、現代に残された史料もないらしい。そしてこれらは、ひとつの源に端を発しているようだ。 それは慶応3年(1867)横浜生まれ、明治から昭和にかけて活動した政治家・講談師の伊藤痴遊が晩年に刊行した『伊藤痴遊全集三十巻・政界表裏快談逸話』の中の文章。 研究者によると全てが嘘であるとは限らないが、どうも信ぴょう性に欠けているようだ。 幕末から明治という時代に女性が一人商売をすることは、やはり想像するだけでも大変そうだ。 |
|
◆お慶の横顔・お慶、清水寺と八坂神社に参詣 |
|
祈祷寺として知られる鍛冶屋町の清水寺。この寺の中門まで上る石段のちょうど中程左手に山門があり、ここをくぐると左奥手に聖天堂がある。 このお堂は、お慶が信仰していた「※歓喜天(かんぎてん)」が祀ってあり、熱心に参拝したといわれている場所。また、聖天堂の帰途、お慶は八坂神社の神職だった博学の小西成則(しげのり)翁を訪れるのが常で、いろいろと教えを受けていたのだという。ちなみに、お慶の大切な書簡などは小西翁がしたためたといわれている。 (※歓喜天/障害をなす魔神を支配する神とされ、事業の成功を祈るために祀られたといわれる仏教の護法神のひとつ) |
 |
|