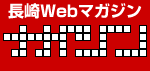|
 |
|
儀門(ぎもん)と呼ばれる孔子廟の正面玄関をくぐり抜けると漂うお香のかおり……。
居留地時代の名残りから現在でも多くの洋館がみられる東山手の中で、レンガ塀からのぞく色鮮やかな極彩色の廟宇(びょうう:廟全体、社殿のこと)はひときわ際立つ。
以前外国人居留地であった場所にあるこの長崎孔子廟は、明治26年(1893)に建立され、度重なる改築を行なってきた。
|
 |
|
戦後改装の際、華南文廟様式という伝統に基づいて建築されたが、昭和57年(1982)に中国政府の絶大な協力、山東省曲阜(きょくふ)孔子廟の助力を受け、琉璃瓦(るりがわら)、石製欄干、龍の御影石、石人、一角獣、孔子像を安置する聖龕(せいがん)、72賢人石像など、すべての資材を中国から取り寄せ完工。
日本で唯一の中国人による本格派の孔子廟である。
その際、廟内の石像や建材など改修用の製品は北京工場で製作されたので中国北部地方のものが一部加わり中国華南と華北の建築様式が合体した廟宇になっている。
さて、このような中国伝統美を受け継いだ長崎孔子廟に訪れたからには『孔子』のことを知らなくては感動も面白さも半減するというもの。
そこでまずはこの孔子廟の御祭神である孔子について早分かりレクチャーといこう。
|
孔子廟の祭神・孔子ってどんな人?
●約2500年前の教え『論語』に迫る●
●孔子の生い立ち
孔子が生まれた年は諸説あるが、魯の国(現在の山東省曲阜)の襄公(じょうこう)22 年(紀元前551)9月28日(新暦)が生誕の日とされている。
つまり、現代より遡ること2500年以上昔のことだ。
孔子の孔は姓、子は先生を意味する尊称で、名前は丘(きゅう)といったのだそうだ。
中国では元服した時に字(あざな)をつけるのだが、これは仲尼(ちゅうじ)。
仲は次男の意味、尼は故郷の近くにある尼丘山(じきゅうざん)から取ったという。
父親は下級役人で孔子が3歳の時に亡くなっている。
また司馬遷の『史記』によると、孔子は正規の結婚でなく生まれた子どもで、幼少期の生活は貧しくあまり明るくないものだった。
そのためか『論語』にある有名な「吾十五にして学に志す」の通り、若くして学問によって身をたてることを決意。
19歳で村役場に勤め、結婚して二児をもうけ、高級官史か政治家になることを目指し一心に勉学に励んだと言われている。
しかしあまり勉学に励みすぎ家庭を顧みなかったためか、あるいはひどく貧乏だったためか、妻は二児を残して離婚してしまった。
そして孔子が30歳を迎えた頃から彼の名声を慕って弟子になるものが集まって来たのだという。
●『論語』って何が書いてあるの?
今では儒教の開祖、聖人君子として崇め奉られている孔子も、上記のような生い立ちを持った生身の人間だったのだ。
それでは孔子=『論語』のワンセットで有名なこの『論語』について誤解はないかな?
つまり『論語』は孔子の著書だと思っている人、いませんか?
『論語』は孔子の死後50年から100年の間に弟子達が孔子と問答をして教えられた言葉、弟子が孔子に自分の意見を語った言葉などを集めた言語録なのだ。
それも、様々な弟子達の問いかけにその弟子のレベルに応じて話をしているため、同様のことでも様々な言い回しをしているとても気安さを感じられるもの。
子曰く(し、いわく)……と始まる20編約500章もの孔子の教えはこれまで中国本土ではもちろん、日本を含む漢字文化圏における道徳の規範とされてきた。
『日本書記』によると日本に伝えられたのは285年だという。
なんと!聖徳太子がつくった「十七条の憲法」の第一条は『論語』を参考にしていると推察されるのだそうだ。
そして江戸時代に入るとさらに今でいう大ブレイク!
そしてその精神世界が人々の胸を打ち、明治期までは生活の規範、人生の指針として根強く日本人にも根付いていた。
しかし、はたして現代ではどうだろう?
ぜひこの孔子廟を訪れたことをきっかけに『論語』に触れ、この疑問の答えを出してみよう。
意外にもあなたの中に『論語』の教えが宿っているかもしれない。
●『論語』に記された代表的教え
では手始めに…いえ、復習に『論語』に記された有名かつ含蓄のある教えを少しだけご紹介。
・「子曰く、巧言令色、鮮なし仁」
(しいわく、こうげんれいしょく、すくなしじん)
「言葉巧みに愛嬌を見せて近づく人にあまり誠実な人はいない。
言葉を飾るな、宝は自分の胸の中に積みなさい」
・「子曰く、故きを温ねて新しきを知る。以って師と為るべしか」
(しいわく、ふるきをたずねてあたらしきをしる。もってしとなるべしか
「古いものを洗い直して学ぶとすばらしい知恵が発見できる」
・「子曰く、己の欲せざる所は、人に施すこと勿かれ」
(しいわく、おのれのほっせざるところは、ひとにほどこすことなかれ)
「自分が嫌なことは、相手も嫌なはず。自分がして欲しくないことは、人にもするな」
|