| 電話095-829-1314(長崎市観光宣伝課) |
●JR長崎駅からのアクセス
市電/長崎駅前電停から蛍茶屋行きに乗車し、公会堂前電停で下車、徒歩3分。
バス/バス停長崎駅前東口から長崎バス親和銀行前経由(中央橋方面行き)に乗車し、親和銀行前で下車、徒歩3。
バス停長崎駅前から長崎市コミュニティバスらんらん(循環バス)に乗車し、本古川町で下車、徒歩2分。
車/長崎駅前から約5分。 |
 |
 |
架設年代は確かではないが、欄干親柱の擬宝珠造りから眼鏡橋(寛永11年・1634)に次ぐ古さで、年代は慶安年間(1650)と推定できるらしい。
何回かの洪水にも耐えていて、構造的にも注目されている歴史的価値が高い橋。
昭和57年(1982)大水害のため半壊、1985年復元。
|
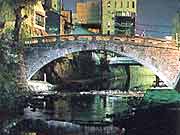 |
眼鏡橋の眼鏡の形を写真に撮ろうと思ったら、この橋から撮るのが一番。
写真を撮るときにこの橋の上を車がブーッと通り過ぎるので注意。
なんと石橋はきれいなだけでなく、車の重さにも耐えられる力持ちでもある。
|
 |
 |
袋橋のたもとに昔(おそらく昭和30年代)停泊していたという牡蠣料理を食べさせる『牡蠣船』のひも?をかけていたと思われる石柱が現存していた。
当時、この橋のしたでどのような風情をかもし出していたのだろうか??
|
 |
 |
 |
寛永11年(1634)、興福寺2代住職だった唐僧・黙子如定が架設した、日本最初の唐風石橋。
江戸の日本橋、岩国の錦帯橋とともに日本三橋の一つ。
昭和57年(1982)大水害のため半壊、1983年復元。
|
 |
 |
 |
平成7年6月10日に建立された、眼鏡橋を架設した唐僧黙子如定(もくすによじょう)の銅像。
眼鏡橋を望むように建っているので、眼鏡橋と同時の記念撮影が不可能なのが残念。
しかし川沿いがすっかり整備される中、存在感を増してきたことには満足しておられるかも?
|
 |
 |
 |
元禄12年(1699)、岡正恒が私費で架設。
何度か架け替えられた後、大正14年(1925)、鉄筋コンクリートの橋になった。
|
 |
 |
 |
寛文元年(1673)架設。1800年架替。
昭和57年(1982)大水害のため全壊。
昭和61年(1986)に昭和の石橋として架設。
|
 |
 |
 |
1681年架設、1721年崩壊。
1804年再架。
昭和57年(1982)大水害のため全壊。
昭和61年(1986)に昭和の石橋として架設。
すすきは草が生い繁るさまをいい、昔この当たりが原っぱだったことから橋の名がついたとか。
|
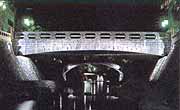 |
 |
 |
1657年高一覧が架設。
1795年に流失。
1801年再架。
昭和57年(1982)大水害のため全壊。
昭和61年(1986)に昭和の石橋として中国・福州市産の花こう岩を使って復旧した。
|
 |
|