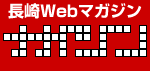 |
|
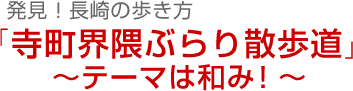 |
|
|
| 「長崎の人はみんなキリシタンで、教会しかないと思ってました」。 あるお寺の住職さんが観光客に言われた一言。 そんなワケはない。中国・オランダ・ポルトガル…。 様々な文化が混在し、今に息づいているのが長崎の町。 そこには当然日本古来の文化もあるのだ。 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
●長崎駅からのアクセス 寺町界隈、最初に案内する清水寺方面へのアクセスは次ぎの通り。 市電/長崎駅前電停から正覚寺下行きに乗車し、終点し、正覚寺下まで10分。 バス/バス停長崎駅前南口から長崎バス田上、茂木行きで崇福寺入口まで10分。 車/長崎駅前から崇福寺通りまで8分。 |
|||||||||
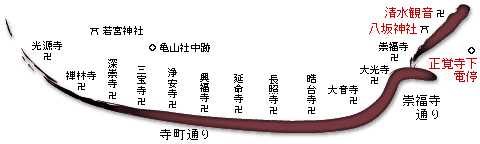 [詳細地図] [広域地図] |
|||||||||
|
|||||||||
明治・大正時代の馬車道として使われていたというこの通りから上を見上げると見事な蔦のベールをまとったアーチ型の中門が見え、夏から冬にかけては鮮やかなピンクのブーゲンビレアの花がこの中門脇に咲き誇り美しい景観を見せている。 |
|||||||||
|
|||||||||
| アーチ型の中門は延命寺、大音寺などほかのいくつかの寺でも見られるもので、中島川の石橋架橋の後造られたものではないかと言われているが、清水寺のこの中門には明和(江戸末期)の文字が刻まれているので、水害で流され復元された石橋よりも古いことは確か。もしかしたら日本最古のアーチ型の建造物かもしれない!?(調査中)。 現存する最古のものではないかと推測される石畳や、石欄をめぐらした本堂前には、澄みわたる青空と素晴らしい景観が広がる。 江戸時代には長崎港を見晴らせる絶景地だったというが、残念なことに現在はビルがここそこに建ち、往時の景色は想像するにとどまる。 しかし、宮司さんのせめてもの策として数年前に電柱を地下に埋め込み、稲佐山方面の市街地を広々と見渡せるようになった。 祈願寺である清水寺は、特に子授け、安産、子育てなど女性にまつわる祈願に御利益があると言われていて、昔から女性の厄払いやお宮参り、七五三の家族連れなどの参拝が多く見られるお寺。 本堂横左手にある弘法大師を祀ったお堂には大きな桜の樹が一本立ち、花見時には近所の人で賑わいをみせるとか。 ここから隣の八坂神社へ通り抜けることができる。 八坂神社と言えばほおずきに彩られた夏の風物詩「祇園祭」が印象的。 こちらの御利益は厄入、厄祓、賀寿清祓の他に、初宮詣、安産祈願等人生の儀礼に関するものが多い。 静寂に包まれた境内にはベンチも置かれ、夏の夕涼みにはうってつけの場所だ。 朱い鳥居をくぐり抜け、崇福寺通りへ向かおう。 |
|||||||||
| <1頁/全3頁>[次の頁へ] |
|
● 取材メモ一覧 ● [清水寺][八坂神社][崇福寺][大光寺][発心寺][大音寺][晧台寺] [長照寺][延命寺][興福寺][浄安寺][三宝寺] [深崇寺][禅林寺] [龍馬通り][光源寺][若宮稲荷神社] ||[詳細地図][広域地図]|| 【もどる】 |





