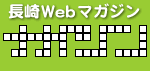 |
|
 |
 小泉八雲の肖像 |
| ■DATA■ 滞在期間/明治26年(1893) 7月21日から二泊三日 連れ/不明 目的/不明 小泉八雲●こいずみ・やぐも/嘉永3年〜明治37年(1850〜1904)。 明治時代の作家。英文学者。ギリシャ生まれのアイルランド人。明治29年(1896)、日本に帰化する以前の名前は、パトリック・ラフカディオ・ハーン。 フランス、イギリスで教育を受け、20歳で渡米。得意のフランス語を活かし、20代前半より文芸、事件報道の現場でジャーナリストとして活躍。40歳の時(明治23年)、アメリカの出版社の通信員として来日するも契約を破棄し、日本にて英語教師となる。松江、熊本、神戸、東京と居を移しながら、日本の英語教育に尽力。『怪談』ほか、海外に日本文化を紹介する著書を数多く遺した。 |
|
日本文化を海外に広め、 祖国に再認識させた帰化日本人 |
|
日本文化を深く理解し、日本をこよなく愛した小泉八雲。彼は、アメリカ滞在中、すでに東洋の神秘さに興味を持っていたそうだ。英語教師として最初に訪れたのは島根県松江。寺院の鐘の音にはじまる人々の生活の音。木造橋を下駄で渡る際に鳴る「カラコロ」という音。宍道湖にかかる朝もや・・・・・・八雲は、昔のままの日本の風景が残る松江に強烈に惹かれたという。名前の「八雲」は、この最初の在住地、島根県松江の旧国名「出雲国」にかかる枕詞、「八雲立つ」にちなんだものといわれている。松江の士族の娘、小泉節子と結婚した明治24年(1891)の11月、八雲は、九州・熊本に移転。現在の熊本大学の前身となる第五高等学校に赴任する。彼が長崎を訪れたのは、この熊本在任中。目的は不明だが、二泊三日の旅だったようだ。7月20日、熊本市を俥で出発した八雲は、熊本城の長塀に沿って流れる坪井川河口の百貫港より船に乗り、21日の早朝3時に長崎港に到着した。そこからは人夫の案内で宿泊先へ。当時外国人居留地として華やぎを見せていた南山手のベルビュー・ホテル(現全日空ホテルグラバーヒルの場所)に投宿する。 |
|
| 「私はありうる最も美しい光の中で、美しい長崎の街を見た」。日が昇る風景に触れた八雲は、この時見た長崎港の日の出光景のすばらしさに感嘆した。早朝、彼は長崎の町へと俥で外出。しかし、お気に召さなかったものが、長崎の町の氏神様・諏訪神社にあった。彼に「私が今まで日本で見たうちで、最も醜いものだ」とまで言わしめたのは、諏訪神社参道入り口に威風堂々と建つ金属製の一ノ鳥居だった。額に「鎮西大社」と記されたこの鳥居は、天保2年(1831)に青銅で造られた。周囲を威圧する大きく近代的な大鳥居は八雲の美意識に沿わなかったのだろう。 |
 八雲が嫌悪感を示した青銅製の大鳥居 <長崎大学附属図書館所蔵> |
| 八雲は、朝食をとり再び外出する。「私の全体の印象は、長崎は今まで見たうちで、最もきれいな港である。---絵のような美しさ、古風な魅力に満ちた---美術家がエッチングし、写真家が撮影するように作られているということである」。八雲の目には、自然と人々が織りなした風景が美しく輝いて見えたようだ。長崎の町の美しい風景に心惹かれた八雲だったが、この地の暑さには耐えられず、あまりの暑さに二十五銭の氷水を四円分も飲み干したという。そして、一刻も早く長崎を離れたく、手に入れたいと考えていた書物も食料品も西洋風の店で見つけたかったものも買わず、7月22日午前3時、長崎港を発った。この時の八雲の来崎目的は定かではないが、和の風情に海外の文化が解け込んだ、異国情緒にあふれる長崎の町を一度はその目で見ておきたかったのかもしれない。 参考文献: 『長崎を訪れた人々〜明治篇〜』 高西直樹著 葦書房 |
|
|
|
|
| 【バックナンバー】 |