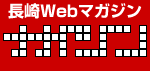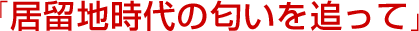|
梶川さんがはじめて居留地跡へ足を踏み入れたのは中学生の時。
美術クラブの先生に連れてこられたのが最初という。
当時螢茶屋近くに住んでいた梶川さんは、いたく感動したこの日のことを今も忘れない。
●梶川さん
現在の市民病院の前にあった出師橋(すいしばし)、湊公園、活水の崖の下辺りにくると空気が変る、居留地の匂いが漂ってくるんです。
もう心がワクワクするんですよ。
その後は休みの日になると一人で電車に乗ったり、歩いたりして度々デッサンに来てましたね。
梶川さんの話からこぼれた「居留地の匂い」が今回のキーワード。
梶川さんが知る居留地跡の魅力を押さえながら、ウォーキング、スタ〜トッ!
まずは電停大浦天主堂下から出発し、南山手へ。
●梶川さん
大浦天主堂へ上る坂道は、にぎやかだけど、それだけに居留地の匂いと風情が消えてしまっているような気がします。
居留地跡を歩くならもっと静かで、情緒ある場所からスタートしてほしいですね。
そこで大浦天主堂、グラバー園方面へ上る観光客の「流れ」に逆らって、一筋先の急な坂道を通って南山手居留地跡へとアプローチしよう。
のぼり上がった正面が南山手8番館、現在南山手町並み保存センターとして開放されている洋館だ。
右方向へきれいに整備された散策道路を歩いてゆくと、左手には現在も住居として利用されている数件の洋館が見えてくる。
右手の海沿いには……立ち並んだビルとビルの間から長崎港が見え隠れする風景に出逢える。
●梶川さん
ドンドン坂から見える港がいいですね。
通りの道筋には数件の今も現役の洋館が現存し、古い石畳の脇には三角の形をした三角溝と呼ばれる溝がある。
水流の速さを調節するために溝の形が上と下とで違うのがおもしろい。
雨が降るとドンドン音をたてて流れるから通称・ドンドン坂。
雨のドンドン坂は、長崎の異国情緒を代表する風景だ。
この坂を下から眺めると「この道はどこへ続いているんだろう」とワクワク感が湧いてくるに違いない。
そして坂を上り振り返ると、坂の延長上に長崎港と造船の町特有の巨大クレーンが見える。
ひとつの坂で二度の感激が込み上げてくるのだ。
ドンドン坂を左に折れると赤いレンガの洋館がある。マリア園だ。
明治30年に設立されたイエズス修道会清心修道院、3階建て赤レンガの養護施設。
町の人々はマリア園と呼んで親しんでいる。
今も昔も門の形色までほぼ変っていない。
右手には大正15年に開業した、杠葉病院(ゆずりはびょういん)の別館、本館が道をはさんで並ぶ。
●梶川さん
この建物の上の鬱蒼と茂った木々の中にはベンチがあるので、この季節、ここでひと休みすると清々しい気分になれますよ。
ベンチから下りて右手に歩いていくとグラバー園の出口付近に出るが、守衛室の前をまっすぐ行くと右に上がる坂段があり入園できるのでご安心を。
グラバー園の出口にある秋の大祭・長崎くんちのビデオ上映、奉納する神輿などを展示する伝統芸能館へと下る坂道から先程来た道を振り返ってみよう。
木々の間からマリア園の洋館見えている。
梶川さんの版画のように、冬の裸木の時だともう少しよく見えるかな。
グラバー園を出て、今度は最近補修工事で白亜に生まれ変わった大浦天主堂へと向かおう。
少しきれいになり過ぎて、以前の天主堂を見なれた人達は多少戸惑っているが、何といっても国宝。風格がある。
この大浦天主堂に向かって左側に小さな道筋がある。
この道に入り、右に上る一つ目の道をのぼってみよう。
するとすぐに梶川さんの版画絵と同じ風景に出会った。
●梶川さん
この細い坂道はとても長崎らしい風景だと思うんです。
坂段のほぼ終わり附近にこんな表示板があった。
「相生(あいおい)地獄坂 体力作り坂(223段)100kcal(上り・70kcal 下り30kcal)」ぜひお試しあれ!
さてさて、ともかく下って車道の方へ行くと、電車の終点・石橋電停がある。
このすぐ横に横断歩道があるのでここを渡り少し進むとオランダ坂が見えて来る。
オランダ坂というと長崎人の間でも活水学院下の坂をそう呼んでいる人が多いが、もともと「オランダさん(当時東洋人以外の外国人を長崎の人はオランダさんと呼んでいた)が通る坂」ということで居留地の坂はすべてオランダ坂と呼ばれていたらしい。
それにしても昔は長崎の冬も雪が積もるほど降っていたが、近頃この絵のような風景はほとんど見かけられなくなった。
しかし、坂道も建物もほとんど当時と変らないのにびっくり!
このオランダ坂沿いには居留地時代に社宅または賃貸住宅として建てられたと推定されている東山手洋風住宅群がある。
現在の建物は復元されたものだが、当時特徴的だったマントル・ピース用の煙突が今も変らず印象的だ。
7棟の洋風住宅群が立ち並ぶ細道の下には極彩色に彩られた
孔子廟の廟宇が見え隠れし、異国情緒溢れる風景に出合える。
●梶川さん
居留地らしい洋風の建物の隣りに、中国らしい鮮やかな赤や黄色。
まさにチャンポンのエキゾチックですね。
孔子廟は昔に比べると綺麗になりましたが、周囲を囲む赤いレンガの塀は昔からのもので、風情がありますよ。
洋風住宅群の間の路地を通り、突き当たりから急な坂段を下り
病院裏を通り抜け、孔子廟がある通りへ進んでみよう。
●梶川さん
どこの町でも路地裏に入っていくと面白い風景に出合えたりするもの。東山手洋風住宅群から孔子廟の通りへ抜ける路地は居留地時代の匂いがかすかに残っている場所ですね。
路地を抜け右手にある昭和会病院横の坂段をのぼり上がると左側に大きなカーブを描いた坂道が現れる。
この辺りにはびっしりと蔦に覆われたりっぱな石垣が多く見られるが、これも居留地時代の名残り。
この坂を上っていくと、右手に日本で最初に建てられた新教会堂(プロテスタント)英国聖会会堂跡がある。
日曜ごとにたくさんの外国人がこの坂道を通り教会に行っていたのだという。
この教会跡横の坂道を上から眺めた風景は東山手風情と呼ばれ、やはり「坂、洋館、港」がセットで眺められるのだ。
活水学院のレンガ塀と居留地名残りの石垣に包まれた石畳の道をさらに上ると居留地境石柱がある。東山手の居留地はここまでという区切りを意味する石柱だ。
そういえばグラバー園の旧三菱第2ドックハウスの傍らにも、南山手の居留地境の石碑が集められていた。
 |
 |
|
少し戻り、活水の門を右手に見ながらすぐ横の坂段を下ろう。
この坂段も穏やかで趣のある坂道。
●梶川さん
観光客でここまで来られる方はなかなかいないんですが、ぜひここを通ってほしいですね
|
 |
このオランダ坂を下りきった通りの左側が今回の「居留地歩き方コース」のゴール地点、野口彌太郎記念美術館(旧英国領事館)。
ここは裏にあたるが、ここからでも入ることができる。
この野口彌太郎記念美術館がある大浦町は、居留地時代、波止場がある港に面した一等地で、各国の商社や領事館などが建ち並び、居留地の中でも最も賑やかな場所だったようだ。
●梶川さん
イギリスに行った時、目にした建物が目新しくなかったんですね。だってこの旧英国領事館のような建物がたくさんあったんです。
「居留地の匂い」がする時代からすると現在の居留地跡の風景は随分変ってしまい、「匂いが薄れてしまった」と梶川さん。
しかし匂いは薄れても、石畳、木造洋館、港を望む眺望。
大木、レンガ塀、それにびっくりする程の組み方で高く積まれた石垣。
歩いていると何かしらか居留地時代を彷佛とさせる風景に出くわす。
異国情緒溢れる息づかいをかすかに感じるのだ。
●梶川さん
あんなにも魅力にとりつかれた居留地跡を最近描かなくなったのは、やはり匂いが薄れてきたから。でももう一度長崎の風景を集大成として描きたいですね。テーマは「教会と港」、「洋館と港」、「洋館と坂」などでしょうか。
長崎の魅力は角度によって見え方が大きく違ってくるということでしょうね。
歩いていると今回紹介したアングルとは違う、美しい風景を見つけ出せるかもしれない。 ぜひ、居留地の匂いを追って南山手、東山手へ出掛けてみませんか?
ちなみに、梶川さん以前の世代、昭和初期の数年間で魅力的な長崎の風景、特に居留地の洋館、中国寺を多く作品にした偉大な人がいた。
長崎出身の版画家・田川憲。彼の作品99点を収蔵する版画展示館(南山手乙9番館)は、散策の途中ぜひ足を運んで欲しいスポット。
大浦天主堂下電停から徒歩5分。
|